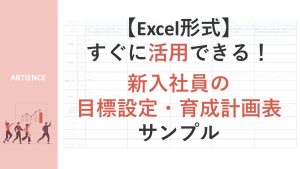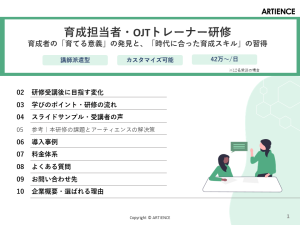-
[ コラム ]
組織の期待通りの成長へ!目的に沿った新入社員研修の内容例【事例付き】
- 「新入社員研修でどんな内容を取り入れれば効果が出るのか知りたい」「毎年新入社員研修をやっているが、成果につながっていない気がする」そんな課題を感じているのではないでしょうか。新入社員が組織の期待通りに成長できるかどうかは、研修の設計次第で大
- 詳細を見る
「新入社員の成長が遅すぎる…」その3大要因と取り組みたい4つの施策【事例あり】
「新入社員の成長が思ったように進まず、売上や業務の効率も上がらない…。」
そんな悩みを抱えている方が多いです。
新入社員の成長が遅れると、現場の負担が大きくなり、組織全体に疲弊感が広がってしまうため、どうにかしたいと思っていることでしょう。
実は新入社員が成長しない原因として「新入社員のスキル不足」「新入社員のマインドセットの未熟さ」「育成体制の不十分さ」があげられます。
これらを改善することで、成長スピードは大きく加速します。
本記事では、新入社員の成長を加速させるために必要な原因の特定と、新入社員の成長スピードを上げる具体的な方法を紹介します。
新入社員の成長を早め、現場社員のストレスを軽減することで、組織全体が前向きに進めるようにしましょう!
目次
1)新入社員の成長が遅い原因:①新入社員のスキル不足
新入社員の成長が遅い原因の1つは新入社員のスキル不足です。
スキルが十分に備わっていない場合、自信を持って取り組めず、業務の進行が滞ります。
スキルを不足について、以下の3つに分けて具体的に説明します。
・基礎スキル不足
・業務に必要な専門スキル不足
・コミュニケーションスキル不足
基礎スキルの不足
新入社員の基礎スキル不足は、業務効率を低下させる大きな要因です。
ビジネスマナーや基本的なPCスキル、時間管理能力が未熟だと、日常業務に必要な作業でつまずくことが多くなります。その結果、業務全体の進捗に悪影響を与えます。
例えば、メール対応の仕方を知らないために返信が遅れ、取引先とのやり取りが滞るケースや、Excelの操作がわからず、データ集計に通常の2倍以上の時間がかかるといった問題が生じます。また、優先順位がつけられず、重要な業務を後回しにしてしまうこともよくあります。
基礎スキルの不足は業務効率が下がる原因となり、そのことによって経験を積める回数も減るため、本人の成長機会を阻害する原因となります。
業務に必要な専門スキルの欠如
専門スキル不足も成長を遅らす要因です。
専門スキルが不足していると、自分より知識のある先輩に頼りがちになり、自分で課題に取り組む機会が減ることで成長のチャンスを逃してしまうためです。
例えば、営業職に配属された社員が、商品知識を十分に理解していない場合、顧客からの質問に対応できず、先輩に対応を変わってもらうことになると成長のチャンスがなくなります。また、企画職では、業界分析や市場調査の手法を知らないために、独自の提案を行えないといった問題が起こります。
そのため、専門スキルを早期に習得することは、自主的な行動を促し、成長速度を加速させる重要な要素です。
コミュニケーションスキルの不足
コミュニケーションスキルの不足も、新入社員の成長を妨げる大きな要因です。
自分の状況や疑問点を上司や先輩に適切に伝えられないと、フィードバックを受ける機会が減り、成長のチャンスを失いやすくなるためです。
例えばわからないことを相談できず、ミスを繰り返してしまい、上司や同僚の信頼を損ねてしまうと、成長のチャンスを貰えなくなることもあります。
適切なコミュニケーションスキルは、成長に必要な適切なフィードバックを得るために重要な要素です。
このように新入社員のスキル不足は成長の遅れにつながるため、早期のスキル習得を支援することが必要です。
2)新入社員の成長が遅い原因:②新入社員のマインドセットの未熟さ
新入社員の成長が遅い原因の2つ目は、新入社員のマインドセットの未熟さです。
マインドセットが未熟では、自分で考えて動く姿勢が育ちません。また、失敗を恐れるあまり挑戦を避けるようになると、経験の幅が狭まり、実力の向上も難しくなります。
マインドセットの未熟さを以下の4つに分けて具体的に説明します。
・主体性の欠如
・失敗への恐れ
・自己効力感の低さ
・キャリアや仕事の意義の欠如
主体性の欠如
主体性の欠如は、新入社員が成長する上での大きな要因です。
主体性を持たず、指示待ちの姿勢が強いと、業務の効率や成果が低下するだけでなく、個人の能力が育ちません。
例えば、上司から課題を与えられるまでずっと待ち続けているような行動は、上司の負担を増やすだけでなく、自身の成長機会を逃す原因にもなります。
主体性は業務における責任感と自信を育て、将来的にリーダーシップを発揮する基盤にもなる、成長に欠かせない要素です。
失敗への恐れ
失敗を恐れる姿勢はも新入社員の成長を妨げます。
失敗を「避けるべきもの」と考えると、未知の課題に挑戦する意欲が低下し、結果として実務経験の幅が狭まるためです。挑戦しなければ成功体験を得ることもできず、自己成長が停滞してしまいます。
例えば、プレゼン資料を作成する際、間違いを恐れて過去の内容を踏襲するだけでは、資料作りの基礎を学べても、より良くするための改善や創意工夫は生まれず、自身の成長にはつながりません。
また、企画提案や新しいアイデアを求められた場合に「失敗したらどうしよう」と考え、自分の考えを表に出さないことも、成長の機会を逃します。
失敗を単なるミスではなく、学びや改善のチャンスと捉えられるようになることが大切です。
自己効力感の低さ
自己効力感とは、「自分にはできる」という自己信頼の感覚であり、新入社員が成長する上で欠かせない要素です。
これが低いと、業務や課題に対して消極的な姿勢になり、挑戦や成果を出す意欲が著しく低下します。
例えば、新しい仕事のチャンスを与えられた社員が「自分には無理だ」と思い込んでいると、断る判断をし、スキルを磨くチャンスを逃してしまいます。
また、会議やディスカッションの場で意見を求められても「自分の意見は役に立たない」と考え、発言を避けることでフィードバックを受けられず、結果的に成長が停滞します。
「自分にはできる」という自信を持たせることが、成長速度を加速させる鍵となります。
キャリアや仕事の意義の欠如
自分の仕事の意義や、キャリアの方向性が見えていないと、業務へのモチベーションが低下し、成長意欲が湧かなくなります。
「なぜこの仕事をしているのか」「将来どうなりたいのか」というビジョンがないと、目の前の業務をこなすだけの受け身の姿勢が定着し、積極的に成長しようとする言動が見られなくなるためです。
例えば、「この仕事が自分の将来にどう繋がるのか分からない」と感じる新入社員は、仕事に対して消極的になり、改善案や効率化の提案をすることもなくなります。また、目的意識がないためにスキルアップのための努力を避け、結果的に成長速度が遅くなることがあります。
キャリアや目的の明確化は、主体的に成長していくマインドを促すために重要です。
このように、新入社員のマインドセットが未熟だと、成長の機会を積極的に得ようとしないため、成長の遅さに影響します。
3)新入社員の成長が遅い原因:③新入社員への育成が不十分
新入社員の成長が遅い3つ目の原因は新入社員への育成が不十分の場合です。
新入社員が成長するためには、適切な指導や支援が必要です。しかし、新入社員の状況に合わせた育成ができていなかったり、現場の育成リソースが不足していると、学びの質が低下し、新入社員の成長を阻害します。
不十分な新入社員への育成が成長を遅らせる下記の5つの要因について説明します。
・育成計画や目標が不明確
・育成担当者の指導スキル不足
・成長機会不足
・入社時研修の効果不足
・上司のリソース不足
育成計画や目標が不明確
育成計画や目標が不明確だと成長が遅れる原因になります。
明確な目標や育成プランがない場合、何を目指して努力すべきか分からず、自分の成長過程を把握できないためです。
例えば、「1年後に身に付いているスキル」が明確でない職場では、なんとなく今ある仕事を新入社員に依頼する状態になりがちです。すると、新入社員は継続的な成長に不安になったり、組織が期待する姿に成長できていない、という結果になりかねません。
新入社員に期待する姿がある場合は、育成計画や目標を明確にし、新入社員も目指す場所を理解している状態にすることが必要です。
育成担当者の指導スキル不足
育成担当者の指導スキルが不足していることも、成長が遅れる原因です。
指導者自身が育成の経験やスキルに乏しい場合、新入社員への適切な支援ができず、必要なフィードバックを適切なタイミングで提供できないことがあります。
例えば、育成担当者が仕事の進め方や手順をすべて細かく指示しすぎると、新入社員は自ら考える機会を失い、指示待ちの姿勢が強まり、成長が停滞する原因となります。
他にも、フィードバックの伝え方を知らないと、新入社員との関係性に亀裂が入り、その後の育成をより難しくさせることもあります。
そのため育成担当者は、適切な指導スキルや経験を持ち、新入社員をサポートできる状態であることが求められます。
成長機会不足
成長機会が不足していると、新入社員は実務経験を積むチャンスを失い、スキルや知識を身につけるスピードが遅れます。
成長は経験によって促進されるためです。
例えば、「この業務はまだ早いから」と新入社員に責任ある仕事を任さない場合、自主的に動く力や実務でのスキルアップの機会を失います。
他にも、データ入力や定型的な作業だけしか仕事をやらしてもらえないと、業務に慣れることはできても、応用力や創造性が育たず、成長速度が大きく遅れる要因となります。
この結果、挑戦する経験が不足し、成長が大きく遅れる原因となります。
入社時研修の効果不足
入社時研修が効果を発揮しない場合、新入社員が業務の基礎を十分に習得できず、その後の成長に支障をきたします。
研修内容が新入社員の業務内容と合致していなかったり、一方的な座学形式で行われたりすると、実務に活用できる知識やスキルが身につきません。
例えば、座学中心の研修で業務の基礎知識を学んだ新入社員が、実際の現場で「どのように活用すればよいのか分からない」と戸惑うケースがあります。現場での対応力が乏しいことで、受け身な姿勢が定着し、主体性の欠如につながります。
配属前の段階で、基本的な社会人としてのスキルをしっかりを身につけておくことで、現場でより成長する機会を得られるようになります。
上司のリソース不足
上司が忙しく、新入社員の指導に十分な時間を割けない場合、成長の機会が失われ、スキルの習得が遅れてしまいます。
適切なフィードバックを受けられなかったり、「教えるより自分でやったほうが早い」と考える上司によって、新入社員が成長機会を奪われることもあります。
他にも、上司が定期的な面談を行えない場合、新入社員が抱える不安がそのままになり、自信を持って業務に取り組めなくなることがあります。
上司が新入社員に適切な時間を割き、しっかりとしたフォロー体制を構築することが求められます。
このように不十分な育成によって新入社員の成長が妨げられている場合もあるため、企業全体で計画的な育成体制を整え、指導者のスキル向上や環境改善に取り組むことが必要不可欠です。
4)新入社員の成長スピードを上げる4つの方法
新入社員のスキルとマインド不足が成長スピードを遅くするため、適切な育成して、成長を促せるようになることが必要です。
新入社員の成長スピードを上げるための具体的な方法として下記4つの観点から紹介します。
・育成担当者のスキルを高める
・新入社員のスキルを高める
・新入社員のマインドを高める
・新入社員と育成担当者の関係性を築く
それぞれの取り組みを組み合わせることで、新入社員の成長を加速し、組織全体のパフォーマンス向上につながります。
育成担当者のスキルを高める
育成担当者が指導スキルを身につけることで、新入社員の成長を効果的に促進できます。新入社員の状況に応じた柔軟な指導が可能になるためです。
育成担当者のスキルを高める具体的な方法として、基本的なスキルを研修で身につけ、その後、人事が育成担当者のサポートをできるように定期的な面談や育成担当者間での情報共有機会を創ると良いでしょう。
育成スキルを身につける研修の実施
育成担当者に、育成スキルの基礎となるティーチング、フィードバック、コーチングの方法を学ぶ機会を提供します。具体的には、ロールプレイやケーススタディを通じて、実践的なスキルを磨きます。これにより、新入社員の状況に応じた柔軟な指導が可能になります。
<参考コラム>
新入社員の教育担当に必要な4つの教育スキルと、悩み解決Q&A
人事と育成担当者で定期的な面談
育成担当者が抱える悩みや課題を聞き出すための定期的な面談を行います。例えば、「新入社員が成長しない理由が分からない」という悩みに対して、具体的な改善策を一緒に考えるフォローアップ体制を整えることで、育成の質が向上します。
研修とサポート体制を組み合わせることで、育成担当者のスキル向上と新入社員の成長を支援できます。
育成担当者間で情報を共有する機会の創出
育成担当者が集まり、情報共有の機会を設けます。それぞれの経験やノウハウを共有することで、新たな視点や解決策を得やすくなり、育成の質を高めることができます。
改めて時間を取ることが難しい場合には、オンラインランチでの実施等も良いでしょう。それぞれが育成における良かった取り組み・悩んでいること を共有し、対話するだけでも、新たな解決策を見つける糸口になります。
新入社員のスキルを高める
新入社員が仕事で成果を出せるようになるためには、スキルを習得する機会を設けることが不可欠です。スキルを身につけることで、業務に必要な知識や実践力が高まり、自信を持って業務に取り組むことができます。
具体的な方法として、研修とOJTが効果的です。
新入社員のスキルを高める研修の実施
研修では、基本的なビジネスマナーやビジネススキルを学び、即実務に役立つスキルを習得できます。
新入社員のビジネススキルを高める際におすすめな研修は以下の通りです。
これらのスキルがあると、仕事を任せてもらえるようになるため、スキルの向上や応用力が期待できます。
<参考コラム>
【事例付き】新入社員研修の内容例!成功のカギを深掘り解説
新入社員のスキルを高めるためのOJTの実施
OJTでは、実際の仕事を通じて、新入社員の状況に合わせて柔軟に育成します。OJTで意識すべきことは以下の4つです。
・依頼した仕事の目的を伝える
仕事の目的を伝えることで、新入社員は「なぜこの仕事をするのか」を理解し、単なる作業ではなく、仕事の意義を感じながら取り組むことができます。これにより、より成果に対して意識的になり、目的に沿ったアウトプットを意識して行動します。
・依頼した仕事へのフィードバックの頻度を上げる
頻繁なフィードバックは、新入社員に自分の強みや改善点をリアルタイムで把握させ、より効率的に学びを深めることができます。具体的でバランスの取れたフィードバックは、自己改善の方向性を示し、成長へのモチベーションを維持します。
・徐々に新入社員が考える余白を増やしていく
徐々に考える余白を増やしていくことで、新入社員は自己判断を行う機会が増え、自分で問題解決を図る力が身につきます。このプロセスを通じて、自立を促せます。
・新入社員の特性を見つけて、活かせるようにする
新入社員の特性を見つけ、個々に合った業務を担当させることで、やりがいを感じながら仕事に取り組めます。自分の強みを活かせる環境で仕事をすることは、モチベーションを高め、より高いパフォーマンスを引き出すことにつながります。
これらを意識して教えることで、より効果的な育成に繋がります。
成長スピードを上げたい場合は、基本的なスキルを研修で学んでもらい、その後OJTで学んだことを活かしながら個々に合わせた育成を促すことをおすすめします。
新入社員のマインドを高める
新入社員が成長し続けるためには、前向きなマインドセットを育むことが重要です。ポジティブなマインドセットを持つことで、仕事の効率や成果に対する意欲も向上し、自己成長を追求する態度が自然と育まれます。
具体的な方法を3つ紹介します。
・新入社員のマインドを高める研修の実施
・新入社員のマインドを高めるためのOJTの実施
・メンターの導入
新入社員のマインドを高める研修の実施
社会人としての自覚を促し、自己成長と仕事を結びつける研修を実施します。
研修を通じて、「なぜ働くのか」を考える機会を提供し、自分なりに言語化することで、成長への主体性を促します。
新入社員のマインドを高める際におすすめな研修は以下の通りです。
研修の中で「社会人としてどうありたいか」や「自身のこれまで・これからの成長」を考える機会を設けることで、新入社員が自らの成長意欲や職業意識を見つける手助けをします。
その結果、自己成長と仕事を結びつけ、前向きなマインドセットを醸成できます。
新入社員のマインドを高めるためのOJTの実施
OJTでは、実際の仕事を通じて、新入社員の状況に合わせて柔軟に育成します。
OJTで意識すべきことは以下の3つです。
・ポジティブなフィードバックを積極的に伝える
新入社員が行った仕事に対して、良かった点や成果をしっかり認めることが大切です。ポジティブなフィードバックを積極的に伝えることで、新入社員は自分の努力が評価されていると感じ、モチベーションが高まります。特に、具体的な成果や努力を褒めることで、次回もその行動を繰り返そうという意欲が湧きます。
・失敗を学びの機会として捉える
新入社員が失敗した場合、その失敗を非難するのではなく、学びの機会として捉えることが大切です。失敗を恐れずに挑戦し続けることが、新入社員にとって重要なマインドセットになります。
・小さな成功体験を積み、成長実感を育む
成功を感じることで、自信を持ち、次のステップに進むためのモチベーションが高まります。成功に自覚的になれていない新入社員に対しては、自分の成長を振り返る機会を作ることで、成長していることを実感してもらうことも必要です。
これらを意識してOJTを行うことで、新入社員は前向きなマインドを持ちながら自信を深め、継続的に成長していけるようになります。
メンターの導入
メンターとは、新入社員に対して心理的な安心感を与えるとともに、仕事やキャリアに関するアドバイスを提供し、モチベーションを向上させる役割を果たす人です。
OJTトレーナーとは別にメンターをつけることで、心理的な安心感を与えます。
メンターと定期的な1on1を行い、新入社員が抱える悩みや疑問を吐き出す場を設けることで、安心して仕事に取り組める環境を整えられます。
メンターからの支援によって、新入社員は自己効力感を高め、積極的に学び、成長する姿勢を強化できるため、長期的な成功へと繋がります。
これらの方法で前向きなマインドセットを育むことは、新入社員が継続的に成長し、仕事で成果を出し続けるために必要不可欠です。
新入社員と育成担当者の関係性を築く
新入社員が成長しやすい環境を作るためには、育成担当者との良好な関係性が不可欠です。
信頼関係があることで、新入社員は安心して学び、成長を促進できます。具体的に以下のような効果があります。
●新入社員から声をかけやすくなる
新入社員は育成担当者に対して、相談や質問をしやすくなり、困っていることや不安を気軽に話せるようになります。これにより、早期に問題を解決でき、学習がスムーズに進みます。
●育成担当者からフィードバックをしやすくなる
良好な関係があると、育成担当者は適切なタイミングで、具体的かつ建設的なフィードバックを行いやすくなります。新入社員はフィードバックを前向きに受け入れ、次に活かすことができます。
●ハラスメントリスクを回避できる
信頼関係が築かれていると、職場でのコミュニケーションがオープンになります。そのため、無意識のうちに誤解や不快感を生むことが少なくなり、ハラスメントのリスクを低減できます。
新入社員と育成担当者の関係性を築くためには、以下の具体的な方法があります。
コミュニケーションの機会を設ける
定期的な1対1のミーティングやチェックインだけでなく、ランチやちょっとした休憩時間に何気ない話をすることも効果的です。自分のことを伝え合うことで、お互いを知るきっかけとなり、関係性の構築に繋がります。
お互いの価値観を知るインタビューをする
新入社員と育成担当者が互いの価値観や働き方に対する考えを共有することで、誤解を減らし、仕事上での期待やスタイルの違いを把握することができます。これにより、双方がより良いコミュニケーションを取りやすくなり、助け合いやすくなります。
これらの方法を取り入れることで、新入社員と育成担当者の信頼関係を深め、成長を促す効果的な環境を作り上げることができます。
新入社員の成長スピードを上げるためには、育成担当者のスキル向上、新入社員のスキル・マインドの育成、そして両者の良好な関係性構築が重要です。それぞれの取り組みを組み合わせることで、新入社員の成長を加速し、組織全体のパフォーマンス向上につながります。
5)【事例】新入社員の成長スピードを再加速させ、受注件数は5倍に
OJTトレーナーの役割強化と育成文化の構築で新入社員の受注件数を5倍にした事例を紹介します。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 業種 | 不動産 |
| 企業規模 | 100名程度 |
| 実施方法 | 新入社員研修、OJTトレーナー研修、新入社員OJTトレーナー合同フォロー研修 |
| 問題 | 組織が急拡大しているが、売上が上がらない |
| 目的 | 新入社員の早期戦力化(売り上げの向上)、育成風土の構築 |
| 得られた効果 | 新入社員の受注件数5倍 育成風土の構築 |
背景
業績が好調で新入社員の採用を開始しましたが、売上が期待に届かず、新入社員の成長スピードが遅いという問題が発生しました。現場社員の負担も増え、不満が高まり、組織の急拡大に対応するためには、早期の新入社員戦力化が必要とされました。
実施内容
主な対策は以下の3つです。
OJTトレーナーの役割強化
OJTトレーナーに対して研修を実施し、より高いコミットメントを求め、責任感を持たせるための役割分担を行いました。
新入社員へのマインドセットの醸成
新入社員に対して、「当事者意識」、「やりがい」、「成功体験」を意識的に育成し、仕事に対する意欲と成果を促進しました。
研修とフォローアップ
新入社員研修やOJTトレーナー研修、新入社員OJTトレーナー合同フォロー研修を実施し、育成体制を強化しました。
結果
適切な対策を行った結果、新入社員の受注件数が前年の5倍に増加し、早期戦力化が実現しました。また、組織内で育成文化が醸成され、定期的な勉強会が開催されるようになりました。
この事例のように、組織課題の本質を明確にした上で、育成態勢と新入社員のマインドセットにアプローチをすることで、新入社員の成長スピードを早めることができます。
6)まとめ・新入社員の成長に物足りなさを感じたらアーティエンスにご相談ください
本記事では、新入社員の成長を加速させるために必要な原因の特定と、新入社員の成長スピードを上げる具体的な方法を紹介しました。
新入社員が成長しない原因として「新入社員のスキル不足」「新入社員のマインドセットの未熟さ」「育成体制の不十分さ」が挙げられます。
それらの原因に対して、適切な方法を検討しサポートしましょう。
適切な対策をすることで、新入社員の成長を加速し、組織全体のパフォーマンスを向上できます。
新入社員に諦めることをせず、新入社員の成長を信じて丁寧に向き合うことが大切です。
アーティエンスでは、新入社員の成長を促す研修を多数実施しています。貴社の状況を丁寧にヒアリングした上で、最適な研修や育成方法をご提案いたします。
ご一緒に状況を整理するだけでも、新入社員の成長をサポートにつながるヒントを得られるかと思いますので、お気軽にお問い合わせください。
新入社員の成長を早め、現場社員のストレスを軽減することで、組織全体が前向きに進めるようにしましょう!