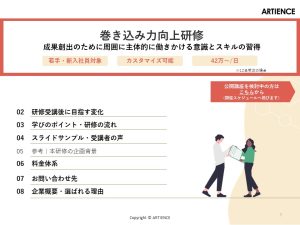-
[ 研修・セミナーレポート ]
2023年5月11日 巻き込み力研修ー公開講座研修レポート
- 2023/5/18作成ー本内容は、2023年5月11日に開催した「巻き込み力研修」の公開講座研修レポートです。受講内容や、受講前と後の変化などをレポートとしてまとめていますので、ぜひご覧ください。(参加企業数:4社、参加人数:18名、集合型
- 詳細を見る
【巻き込み力研修】若手・新入社員が受け身姿勢から脱却し、成果を最大化するために
更新日: ー
作成日:2022.12.6
「うちの若手社員は、周囲を巻き込む力が弱い」
「何でもかんでも一人で抱え込んでしまう。もっと巻き込み力があれば…」
「言われたことしかしない。御用聞きになる。巻き込み力を養ってほしい」
このようなお話を、人事・経営者の方や現場管理職の方々からよくお聞きします。
若手・新入社員の巻き込み力が足りないという問題意識を持っている組織が多くあります。その際、巻き込み力を養う研修を行いたいと思うのは、自然な流れです。
そこで本コラムでは、そもそも「巻き込み力とは何か?」、そして巻き込み力を養うために、どのような研修を行っていけばいいかについてお伝えしたいと思います。
本コラムを最後までお読みいただけると、自組織にとって、どのような巻き込み力研修を実施したらいいかが分かります。
目次
1)巻き込み力研修の目的
当社の巻き込み力研修は、「『周囲を巻き込み、成果を出す』楽しさの実感と具体的なスキルの習得を目的としています。
巻き込み力を養うためには、当人の当事者意識と主体性を持ち、周りへ働きかけることが必要です。巻き込む楽しさ、成長実感、自己効力感といった感覚も持ち合わせなければ、自ら周囲を巻き込もうという姿勢は継続されにくくなるためです。
具体的には、巻き込み力を養う際に、「巻き込むことは楽しくて、成果につながる」ということを体験します。そして、具体的なスキルを実践しながら「巻き込むために活かせる自身の強みと、解決すべき課題」を見つけていきます。
新入社員・若手社員・中堅社員が「周囲を巻き込まない(巻き込めない)」のは、次の理由からです。
・そんなこともわからないのか、できないのかと思われたくない(無知・無能)
・迷惑がられたり、嫌な顔をされたらどうしよう(邪魔)
・今のままでいいのに余計な仕事を増やすヤツと思われたくない(ネガティブ・邪魔)
・一生懸命働きかけても、否定されたら怖い(邪魔)
これらは、心理的安全を妨げる4つの要素(無知・無能・邪魔・ネガティブ)でもあります。
2)巻き込み力研修の対象者は新入社員・若手社員
巻き込み力研修の主な対象者は、新入社員や若手社員です。 仕事経験の少ない新入社員・若手社員は、周囲の効果的な巻き込み方を知らないためです。
例えば、次のような課題・悩みに、巻き込み力の醸成は効果的です。
・仕事を一人で抱え込んで、パンクする
・テレワークで、自分からコミュニケーションを取るのが苦手
・他者の力を借りるのが苦手で、上司・先輩側からフォローしないと仕事が進まない
・社内外の人に言われた事を、そのまま上司・先輩に伝えるだけの伝書鳩になっている
上記の課題や悩みを解決していくために、新入社員・若手社員が、「『周囲を巻き込み、成果を出す』楽しさを実感し、自身の強みの活かし方、課題との向き合い方を学ぶ」ことで、巻き込み力を高めていく必要があります。
若手・新入社員の巻き込み力に悩んでいる人事責任者様・担当者様へ
こんな悩みをおもちではありませんか?
- 若手社員の巻き込み力が低く、どう対策を打つべきか分からない
- 巻き込み力を高める研修の具体的な内容を知りたい
- 巻き込み力が高まった事例を知りたい
当社では、経験豊富な担当者が貴社の課題感や予算にあわせ、巻き込み力を高める研修を企画いたします。まずはお気軽にご相談ください。
3)巻き込み力研修で期待される2つの効果
巻き込み力研修で期待される効果は、次の2点です。
・「言われたからやる」のではなく、「よりよいものを」の意識に変わる
・「顧客や上司は、敵ではなく、共に価値を最大化していく仲間」と捉える
新入社員や若手社員によくある5つの課題・お悩みに対し、巻き込み力研修を通じて次のように改善・解決をしていきます。
| よくある新入社員・若手社員の課題・悩み | 新入社員・若手社員がよくある 課題・悩みを解決した後の姿 |
|---|---|
| 言われたことは、一生懸命行う | 言われたこと以外もよりよくするための働きかけを行う |
| 仕事を抱え込んで、パンクする | 周りに頼りながらも、助け合う |
| テレワークのため、自分からコミュニケーションを取るのが苦手 | よりよい仕事をするために、周りに遠慮せず自ら働きかける |
| 人の力を借りるのに抵抗感があり、いつまでたっても上司や先輩社員のフォローが必要になる | 上司・先輩社員の力を借りながらも、自らもよりよくなるための行動を行う |
| 顧客とのコミュニケーションや社内のPJでも、ただの伝書鳩になっている | 顧客・上司との共創・協働を大切にして、よりよくするための意識と行動がある |
巻き込み力研修では、『「言われたからやる」ではなく、「よりよいものを」の意識に変わる』と、『顧客・上司は、「敵ではなく、価値を最大化する仲間」と捉える』という効果を得るために実施することが必要です。
4)巻き込み力研修の具体的な内容
巻き込み力研修の内容は、目的と効果を最大限得るために、シミュレーションワークを行いながら、新入社員・若手社員自身の課題と向き合うことが必要です。
座学では、巻き込み力の重要性を理解できていても、具体的にどのように実践していいか分かりません。ケーススタディ(個人ワーク・グループワーク・発表・講師からのフィードバックと解説)で学んだ場合は研修内での「周囲を巻き込む経験」が少なくなります。
シミュレーションワークでは、例えば、講師が上司・顧客役となり、受講生が部下役になりワークを進めます。社内で行う場合には、研修を次の作りにすると、巻き込み力の重要性を理解し、行動変容につながるでしょう。
例えば、アーティエンスの巻き込み力研修では、講師が2名体制で
・上司役
・お客様役
を担います。受講者である若手社員・新入社員は、シミュレーション内の課題である案件を、上司・お客様を巻き込みながら前に進め、成果に繋げていきます。

5)【3つの事例】巻き込み力研修を通じて得られた変化
前章までは巻き込み力研修の概要についてお伝えしてきましたが、よりイメージしていただくために。3つの事例をお伝えしていきます。
1)配属前に「現場の厳しさ」を体感し、”健全な不安”の醸成
大手IT企業(5,000名程度)に対して、新入社員の6月末の配属前に実施した事例です。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 業種 | ITサービスの保守運用 |
| 企業規模 | 5,000名程度 |
| 実施時期・方法 | 6月末2日間。講師派遣型研修 |
| 課題意識 | 新入社員研修は、人事が丁寧にレクチャーをするが、現場は厳しさがある。新入社員研修で学んだことを実践することで、その厳しさが乗り越えられることを知ってほしい。 |
| 巻き込み力研修の実施理由 | 新入社員研修で学んだことを、配属前に実践し、その上で成功体験・失敗体験を得ることができる。 |
| 得られた効果 | 多くの管理職から、今年の新入社員は、積極性があるという発言があった。 |
「配属前のキラキラした想いを持った新入社員が、配属半年後のフォロー研修では、暗い顔をしていることが多い」、「他のグループ会社と比べて、離職率が高いのも課題」といった課題感をお持ちでした。
当社へご相談いただいた際は、「以前は配属前に、現場の厳しさを教える研修を実施したが、新入社員が萎縮して、研修への不満が出てしまった。確かに理不尽な研修ではあったが、現場の厳しさも知ってほしい。どうしたら解決できるのか?」といったお話がありました。
ご一緒に企画を進めていくと、人材開発チームの想いとして「新入社員は、課題や現場と向き合いながらも、自分を信じて、仕事を楽しんでほしい」とが言語化されました。
上記想いを体現していくために、配属前に巻き込み力研修を実施しました
新入社員は、上司役や顧客役の講師に戸惑いを持ちながら、ワークを進めていましたが、良い仕事をすることへの意識を持った段階で、研修のワークではなく仕事として捉えて没頭していきました。
二日目には、一日目の成功体験・失敗体験を振り返りを行い、現場でどのように活かすかを考えていきました。新入社員からは、「配属前の今の気持ちは、心配が3割、楽しみが7割」というような声もあり、前向きな発言で溢れていました。人材開発チームからも、「ただキラキラしているのではなく、健全な不安もあり、あとは現場で頑張ってほしい」ということでした。
研修後、現場の管理職から「今年の新入社員は、積極性がある」、「率先して先輩社員の手伝いをしている」、「お客様からサンクスメールをもらった新入社員もいる」などの声が人事に届いたそうです。
2)独断的な進め方から、上司と共に成果を出す進め方に変化
出版社(100名程度)に対して、新入社員のオンボーディング支援として実施した事例です。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 業種 | 出版社 |
| 企業規模 | 100名程度 |
| 実施時期・方法 | 5月中旬1日間。公開講座 |
| 課題意識 | 現場では、徒弟制度や「背中を見て学べ」という習慣がある。現場の改善も必要だが、新入社員の耐久性も養いたい。 |
| 巻き込み力研修の実施理由 | 新入社員自身が働きかけるための意識を養い、行動する経験を持ってほしい。 |
| 得られた効果 | 新入社員から、「仕事が楽しい。上司・先輩社員は怖い時もあるが、いい仕事をしたとき一緒に喜べる」という発言あり。 |
出版社ということもあり、志望度がとても高い新入社員が入社しますが、リアリティショック(入社後のギャップ)を受けるという現実がありました。
「新入社員は、みんな優秀だが、出版社独特の仕事の進め方に戸惑い、立ち上がりが遅くなる。現場の教育もしたいが、どうしても現場の業務量を考えると、新入社員の指導の方がやりやすい」というお話でした。
「9月から配属ということもあり、せめて8月まで配属前研修として、できる限りの支援をしていきたい」というご相談をいただきました。そこで、4月から8月まで当社の新入社員研修の公開講座を受講していただくことになりました。
6月から書店へ赴き、実業務を学ぶということで、巻き込み力研修を受けるのは、とてもタイミングが良いという話になり、新入社員に対して書店に行く前の重要な研修と位置付けて、受講を促しました。
「より良いものを作る」という意識は、元々強い新入社員が多いものの、独善的になる傾向がありました。この時に、「顧客や上司はどう考える?」、「彼らの期待に応えながらも、自分たちの想いや意見はどう伝えていくといいのだろうか?」とフィードバックしながら、ワークを進めていきました。
フィードバックによって、視点が変わり、どんどんアウトプットの質が高まっていき、「自分がいいと思うものを、説得するだけではだめだと気付いた」と話す新入社員もいました。
アフターストーリーとして、配属後に人事責任者の方が新入社員と一緒に飲んだ際に、「仕事が楽しい。叱られることもあるし、厳しいなと思うこともありますが、上司と一緒にいい仕事をするのは、最高です」と話されていたそうです。
3)若手社員の「言われたことしたやらない」受け身姿勢を解消
中堅IT企業(1,000名程度)の若手社員を対象に、受け身姿勢を解消するためのフォロー研修として実施した事例です。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 業種 | SIer |
| 企業規模 | 1,000名程度 |
| 実施時期・方法 | 3年目社員に対して9月2日間。派遣型研修 |
| 課題意識 | 若手社員が受け身であり、言われたことしかしない。離職率も高い。管理職からは、「使えない」という発言が出ていたり、経営陣からは離職率を下げるように言われている。 |
| 巻き込み力研修の実施理由 | 若手社員がいきいきと働くためのヒントが欲しい。そして、起きなくていい離職率を下げていきたい。 |
| 得られた効果 | とてもおとなしい社員が研修後、「会議で、自ら発言があった」と上長から連絡があった。離職率の問題はまだ解消できていないが、人事部への相談が増えた。 |
「若手社員の離職率が高い。また、受け身で言われたことしかしない」という課題感をお持ちでした。また、管理職からは「今の若手社員は使えない」と言われてしまう状態でした。
研修当日、受講した若手社員は皆大人しく、覇気がない状態でした。シミュレーションワークでも、基本言われたことしか行わないという状態でワークが進んでいきました。
ほとんどのグループが、顧客の期待程度のアウトプットや期待にも満たないアウトプットでした。
研修2日目も覇気がない状態が続き、「ただ言われたことをやる」というスタンスでした。
そのため、人事担当者と相談し、プログラムを途中で変更し、まずは彼らの今の想いや感情などを話すという対話をしていきました。その時に彼らから、下記のような発言が出てきました。
・忙しい中、このような研修をやっても意味がない
・会社を辞めたいと思っているから、研修を受ける気がない
・研修でいいことを言われても、現場は違う
・自分たちの上司は無関心で、頼り甲斐がない
人事チームの顔は曇っていましたが、この瞬間に初めて三年目社員は本音を言い、自身と組織と向き合っていました。そんな中、受講生の一人から、以下の発言がありました。
「昨日の巻き込み力研修で起きたことは、実際の現場でも起きていること。クライアントからの要望はめんどくさいし、上司は小言ばかり。でも、これは自分たちの取り組む姿勢が一番の問題なのではないか?いい仕事をしようなど思っておらず、ただ楽をしようとしている」
この発言から、自分たちと組織の課題は何か?を、徹底して話していき、どうやって私たちは周りを巻き込んでいくといいかという話をしていきました。そして、最後の全体シェアの際に一番おとなしかった女性の受講生が声を震わせながら、「私は、人前で話すのが苦手です。でも本当は変わりたいし、もっと成長したい」と話し、自身がこの研修で学んだことを伝えてくれました。
アフターストーリーとして、最後にシェアをした女性社員の上司から、人事チームにお礼のメールが来たそうです。
「会議で発言をしたことなんてなかった○○さんが、発言してくれた。びっくりした」
巻き込み力研修を通して、認知変容と行動変容が起きていました。そして、本研修を通じて、人事と若手社員の繋がりが強くなり、退職を考えているなどの悩みが来るようになったそうです。
3つの事例をお伝えしましたが、巻き込み力研修はさまざまな状況にあわせて実施ができます。
6) 巻き込み力研修を実施する際に意識したい3つのポイント
巻き込み力研修を実施する際に意識したい3つのポイントをお伝えします。
1)実施のタイミング
実施タイミングとしては、節目で行うことをお勧めします。巻き込み力研修を通して、次のステージに行くという意識を創りやすいためです。具体的には、配属直前や半年後のフォロー研修などで行うとよいでしょう。
ただし、公開講座を利用される場合は、日程が決まっているため、節目ではない場合もあります。先ほどの2つ目の事例でも、まだ配属前までには時間があり節目ではありませんでした。
その場合は、なぜこのタイミングなのかという意味付けを受講生にしっかり伝えることが必要です。先ほどの2つ目の事例では、書店での実業務前のタイミングだったため、書店での実業務と研修内容の繋がりを考え、どのような学びを得てほしいか、研修前に受講生に伝えました。
その結果、受講生もより目的意識を持って受講していただけました。
2)研修の世界観を構築するための準備
巻き込み力研修の世界観を創るための準備は、惜しまないことが重要です。シミュレーションワークを通して学ぶため、世界観に没頭できないと、学びが半減するためです。
例えば、講師に上司役・顧客役がいる場合は、研修前や休憩時間に彼らが話していたりすると、受講生は一気に熱量が下がります。これは、講師と人事が彼らの見えるところで話していることでも起きます。
3)講師のレベル(フィードバック)
「巻き込み力研修での講師のレベル(フィードバック)」は、的確でありながら、現場でも起こり得るフィードバックである必要があります。
適切でないと学びが生まれませんし、現場で起こり得るフィードバックでないと、受講生は素直に受け止められません。フィードバックも適切ながら、研修という状況よりも、現場で起こり得るフィードバックを意識してできる講師のレベルが求められます。
よくある失敗としては、現場を意識しすぎて、悪い意味で受講生が迷ってしまったり、適切なフィードバックをしたことで、カンペを読んでいるような状態になり、研修という文脈になってしまうということです。
7)まとめ ~巻き込み力研修を実施するならアーティエンス~
本コラムでは、巻き込み力研修について説明しました。
① 巻き込み力研修の目的は、『周囲を巻き込み、成果を出す』楽しさを実感し、自身の強みの活かし方、課題との向き合い方を学ぶこと
② 巻き込み力研修の対象は、新入社員・若手社員がおすすめであること
③ 巻き込み力研修の効果は、下記2点であること
・「言われたからやる」ではなく、「よりよいものを」の意識に変わる
・顧客・上司は、「敵ではなく、価値を最大化する仲間」と捉える
④ 巻き込み力研修の内容は、目的と効果を最大限得るために、シミュレーションワークを行いながら、新入社員・若手社員自身の課題と向き合うことが必要であること
これらの内容をイメージするために、3つの事例をお伝えしました。
そして、巻き込み力研修を実施する際の注意点も3つお伝えしました。
ロジカルシンキングや、ビジネスマナーなどと違い、巻き込み力とは抽象的な内容です。だからこそ、目的・対象・効果・内容などを明確にしていく必要があります。
当社の巻き込み力研修は、10年以上も提供しており、1回の大幅なアップデートをしています。時代にあわせて、より今の新入社員・若手社員の巻き込み力を高める内容になっています。
当社の巻き込み力研修にご興味がある方は、ぜひご連絡いただければと思います。みなさんの組織の新入社員・若手社員の巻き込み力が高まることを願っております。
若手・新入社員の巻き込み力に悩んでいる人事責任者様・担当者様へ
こんな悩みをおもちではありませんか?
- 若手社員の巻き込み力が低く、どう対策を打つべきか分からない
- 巻き込み力を高める研修の具体的な内容を知りたい
- 巻き込み力が高まった事例を知りたい
当社では、経験豊富な担当者が貴社の課題感や予算にあわせ、巻き込み力を高める研修を企画いたします。まずはお気軽にご相談ください。