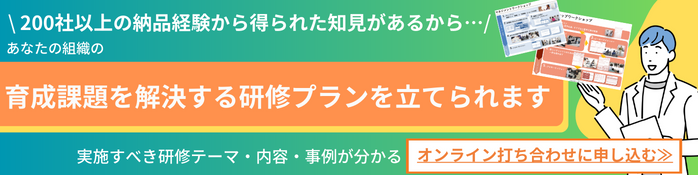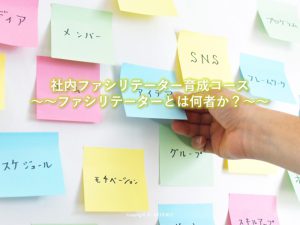- [ 研修・セミナーレポート ]
2022年8月23日 ファシリテーター研修1日目ー公開講座研修レポート
- 2022/8/30作成ー 本内容は、2022年8月23日に開催した「ファシリテーター研修1日目」の公開講座研修レポートです。受講内容や、受講前と後の変化などをレポートとしてまとめていますので、ぜひご覧ください。(参加企業数:3社
- 詳細を見る
人事が研修講師をする意味、メリット・デメリット│研修品質の向上を行うために
更新日: ー
作成日:2023.6.2

2023/8/29更新ー 2023/6/2作成ー
「人事が研修講師を行うことで、研修の内製化を進め、コスト削減を行いたい」
「社内研修の品質を高めたい。そのためには、人事が研修講師として何をすればいいのだろう」
上記のいずれかの問題意識から、本コラムにたどりついたのではないでしょうか。
どちらの問題意識であっても、人事が研修講師を行うことのメリット・デメリットや、何をどのように学べば良いのか等を知りたいという背景があるのではないでしょうか。
そこで、本コラムでは、「人事が研修講師を行う上で、知っておかなければならないこと」をお伝えします。そして最後までお読みいただくと、人事が研修講師を行う上で、必要なポイントを抑えることができます。
研修講師に必要なスキルもお渡し!
>アーティエンスの「ファシリテーション研修」一覧はこちらから
目次
1)人事が研修講師をする意味は「人材開発・組織開発への当事者意識・主体性を高めていく」ため
人事が研修講師をする意味は、「人事が人材開発・組織開発への当事者意識・主体性を高めていく」ためです。
人事が研修講師を行うことによって、人事部全体で、今まで以上に人材開発・組織開発への関心度合いが上がります。そして、講師登壇をする本人が、より当事者意識・主体性を発揮しなければならない状態になります。「人事が研修講師をする意味」を明確に伝えておくことで、人事が研修講師を登壇する際の準備や伝えるメッセージなども変わってくるでしょう。
例えば、ビジネスマナーの研修を人事部門の若手社員が担当したとします。
その時に「人事が研修講師をする意味」を伝えていなければ、一般的なマナーを伝えて終わりということも出てきます。
「人材開発・組織開発をより推進するために、人事が研修講師を行う」という意味を伝えていた場合は、ビジネスマナーを通して、組織開発を行うという意識も出てくるかもしれません。挨拶が少ない状態になっている組織であれば、「新入社員から、挨拶で組織を明るくしよう!」と伝えるかもしれません。
このように人事が研修講師を行う際、「人事が人材開発・組織開発への当事者意識・主体性を高めていく」ために行うことを、強い目的意識とすることで、研修効果は大きく変わります。
経営者や人事責任者が、「人事が研修講師を行う目的意識」を伝える際は伝え方に注意が必要です。なぜなら、この伝え方によって、研修効果が大きく変わるためです。
例えば、下記2つの伝え方の例をお伝えします。
・伝え方1:コスト削減のために、人事が研修講師を行う
・伝え方2:人材開発・組織開発をより推進するために、人事が研修講師を行う
・伝え方1:では、特に目的意識もなく、淡々とこなすことになるケースも多いでしょう
・伝え方2:では、人材開発・組織開発をより推進するために何が必要かを考えて、研修講師を行うでしょう
人事責任者や、経営者は、この目的意識の取り扱いに注意しなければなりません。また人事の若手が、上司や経営者から「コストをかけられないから、研修講師をして」と言われたとしても、組織へのインパクトや自身のキャリアのことを考えたときに、「人材開発・組織開発をより推進するために、自分は研修講師を行う」という考えを持つ必要があります。
2)人事が研修講師を行うことのメリット・デメリット
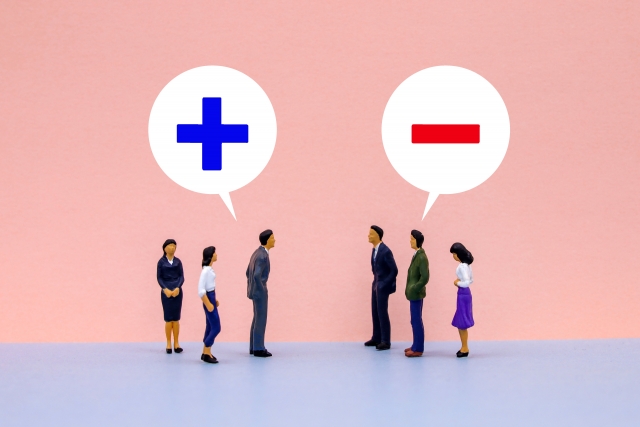 人材開発・組織開発の観点において、人事が研修講師を行うことのメリット・デメリットをお伝えします。
人材開発・組織開発の観点において、人事が研修講師を行うことのメリット・デメリットをお伝えします。
5つのメリット
実際の業務と連動した指導ができるため、人材開発・組織開発が推進される
今起きている自組織の課題に対して、すぐに対応できます。例えば、若手社員の営業力が落ちているということであれば、実際現場で起きる状況を踏まえて、ロールプレイングを行うことも可能でしょう。
若手社員の離職率が高くなっている場合でしたら、会社で何が起きているかを、若手社員と対話をしてもいいでしょう。そして、会社として対策を打つこともできます。
もっと予算をかけるべき研修の方に予算を費やすことができる
講師としての難易度が低いと言われる新入社員研修や、若手社員研修に対して、人事が研修講師として登壇することで、難易度が高いと言われる管理職や経営者にむけての研修やワークショップに予算をより割くことができます。
人材開発・組織開発に対して、人事のコミットが上がる
「人事自身が研修講師をする」となったとき、自身が準備し、登壇するということになります。そのため自分で考えて、対応する必要が出てくるため、コミットが上がっていきます。
組織の状況にあわせて、臨機応変に進めることができる
スケジュールや内容を臨機応変に変更することが可能です。会場手配ができなかったから、オンラインでの実施ということも可能になるでしょう。
人事にとって、新しいキャリアとして示すことができる
研修講師は、独立もできるため、市場価値も上がります。講師として、副業などもできます。
4つのデメリット
人材開発・組織開発のプロフェッショナルのスキルがない
誤った手法でアプローチしてしまうこともあります。より組織課題や事業課題を悪化させたり、また短期的な目線での人材開発・組織開発になるケースも見られます。
例えば、「厳しい研修をして、喝を入れよう」などは、悪手になる場合が多いです。厳しい研修は、学術的には効果が低いと言われており、多くの場合、悪影響の方が大きいと言われています。
詳しい内容は、下記コラムをご参考にしてください。
・厳しい管理職研修─本当に必要か否か|リスクと必要な3つのステップ
・新入社員研修に必要な厳しさとは何か?│厳しい新入社員研修の必要性
対策としては、人事が人材開発・組織開発に対して、学び続ける必要があります。
講師の品質低下や、講師パフォーマンスにばらつきが出る
講師としてのトレーニングをしっかり行っていなければ、講師の品質は低くなります。また感覚で行っていると、講師のパフォーマンスがいい時もあれば、悪い時も出てくるので、安定的なパフォーマンスを発揮できません。
対策としては、人事が研修講師としてのトレーニングを受ける必要があります。
社内講師の業務負荷が増え、やらされ感が生じる
「業務量が多い場合に追加で研修講師の仕事が増える」、また「研修講師をやりたくない」というメンバーに対して、業務負担になり、やらされ感が生まれます。
対策としては、業務量の調整や、研修講師を行うための意味づけを共に行っていくといいでしょう。
「組織の状況にあわせる」という言い訳ができてしまう
経営陣から、「再度スケジュールを調整してほしい」や、「現場の管理職から、○○さんは急遽顧客との打ち合わせが入ったので、欠席で」などの話が出る場合があります。
対策としては、年間スケジュールを先に決めて、経営陣から欠席ができないように促していく必要があります。
3)人事が研修講師を行うにあたって、よくある質問
人事が研修講師を行うにあたって、よくある質問に関して、それぞれ回答しています。
質問1:研修プログラムの開発は、講師が行うべき?
登壇する講師が開発することをお勧めします。自身で開発した研修プログラムであれば、登壇の品質も上がるでしょう。ただし、工数の問題もあるので、他の人事の方が創ってもいいですし、研修会社によってはプログラムのレンタルや販売を行っているので、それを用いてもいいでしょう。
下記コラムを読んでいただくと、研修プログラムの作成のヒントになるかもしれません。
研修講師を育成する際に知っておきたいこと│基礎スキルと応用スキル
※ 「1)【基礎編】研修講師を育成する際に、必ず抑えるべき内容」の「①研修の企画力を身に付ける」を読んでいただけるといいと思います。
質問2:人事が講師、現場社員が講師、外部研修会社に依頼、この3つをどのようにすみ分ける?
それぞれ回答していきます。
「人事が講師」を推奨するもの
・新入社員研修
・若手社員研修
・管理職研修
・社員全体のワークショップ
「現場社員が講師」を推奨するもの
・専門スキル
「外部研修会社に依頼」を推奨するもの
・社内研修で補えないもの
・費用対効果を考えた際に外部に依頼したほうがいいもの
※ 高い専門スキルが必要なものは、社内で行うのは避けたほうがいいでしょう。
理由は、誤った方法や考えを伝えると、悪影響があるからです。具体的には、メンタルヘルス関連や、法律関連などは、誤った時点でリスクが高まります。またコーチングやファシリテーションなども、高い専門スキルが求められるので、専門家から学ぶといいでしょう。
より具体的な例として、新入社員研修を通して、お伝えしていきます。
社内のルール説明や、各部署の説明などは、人事が行うことが必須になります。
・「現場社員が講師」を推奨するもの
新入社員がまず覚えたほうがいい専門スキルは、現場が行うといいでしょう。
※ 人事が行う場合もあります。
・「外部研修会社に依頼」を推奨するもの
学生から社会人の切り替えを行うために、社内では言いにくいことを外部講師を通して、フラットに伝えてもらうなどがあります。
このように使い分けるといいでしょう。また、「費用対効果」に関しては、新入社員や若手社員、管理職が少ない場合は、外部研修会社の公開講座を受講するのもいいでしょう。
質問3:人事が講師を行う場合、講師になるための研修を受けたほうがよい?
受講されたほうがいいでしょう。そのほうが、研修の品質が大きく変わるためです。
知識を一方的に講義スタイルで行うものでしたら、講師としてのトレーニングを受けなくてもいいと思いますが、インタラクティブな対応を求められる研修でしたら、講師になるためのトレーニングは必須だと考えます。
質問4:人事が講師を行う場合、どのようなトレーニングを行ったほうがよい?
まずは研修講師として、ベーシックスキル(企画力、講師基礎スキル)を学ぶといいでしょう。そのあとに発展的なスキル(ファシリテーションスキル)を学ぶといいでしょう。
研修講師を育成する際に知っておきたいこと│基礎スキルと応用スキル
研修講師として独立できる人とは?独立に向けた5ステップと成功の鍵
ファシリテーションスキルの基本と磨き方│上手な場作りの秘訣とは?
4)まとめ
本コラムでは、人事が研修講師として必要なポイントを、お伝えしていきました。具体的には、下記内容をお伝えしました。
・人事が研修講師を行うことの人材開発・組織開発の観点でのメリットと、デメリット
メリット・デメリットに関しては、下記のとおりです。
・より業務に連動した指導ができるため、人材開発・組織開発が推進される
・より予算をかけたほうがいい研修やワークショップなどの質が上がる
・人材開発・組織開発に対して、人事のコミットが上がる
・組織の状況にあわせて、臨機応変に進めることができる
・人事にとって、新しいキャリアとして示すことができる
【デメリット】
・人材開発・組織開発のプロフェッショナルのスキルがない
・講師の品質が低い。講師パフォーマンスにばらつきが出る
・業務負担になり、やらされ感が生まれる
・組織の状況にあわせるという言い訳ができてしまう
「人事が研修講師を行う上で、知っておかなければならないこと」を、理解いただけたと思います。人事が研修を行うことで、あなたの組織の人材開発・組織開発に素晴らしい影響があることを願っております。人事が研修講師を行うことに関して、ご興味がある方はぜひご連絡ください。