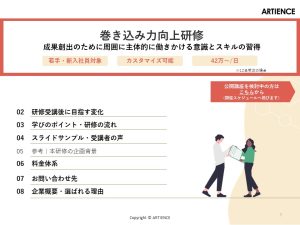-
[ 研修・セミナーレポート ]
2023年5月11日 巻き込み力研修ー公開講座研修レポート
- 2023/5/18作成ー本内容は、2023年5月11日に開催した「巻き込み力研修」の公開講座研修レポートです。受講内容や、受講前と後の変化などをレポートとしてまとめていますので、ぜひご覧ください。(参加企業数:4社、参加人数:18名、集合型
- 詳細を見る
【事例あり】受け身姿勢を打破し、共創意識を育てる巻き込み力研修
更新日:
「うちの若手社員は、周囲を巻き込む力が弱い」
「何でもかんでも一人で抱え込んでしまう。もっと巻き込み力があれば…」
「言われたことしかしない。御用聞きになる。巻き込み力を養ってほしい」
このようなお話を、人事・経営者の方や現場管理職の方々からよくお聞きします。
仕事で成果を上げるために不可欠なのが「巻き込み力」です。チームでの連携が求められる中、単独で仕事を進めることはできません。
特にまだ知識や経験の浅い新入社員や若手社員にとって、周囲を巻き込みながら仕事を進める力は、成功の鍵を握る重要なスキルです。
本コラムでは、巻き込み力研修の目的や効果、実際の研修内容について詳しくご紹介します。巻き込み力研修によって課題を解決した3つの事例も紹介します。
若手・新入社員が受け身姿勢から脱却し、成果を最大化させるために、巻き込み力研修を効果的に活用しましょう。※巻き込み力:「周囲に主体的に働きかけられる意識とスキル」と、弊社では定義しています。

大学卒業後、大手通信会社、アルー(株)勤務後、2010年にアーティエンス(株)を設立。業界歴17年。大手企業から、中小企業、ベンチャー企業の人材開発・組織開発の支援を行っている。専門分野は、組織開発、ファシリテーション。
目次
1)巻き込み力研修の目的と効果
巻き込み力研修の目的は、周囲を巻き込み、成果を出す人材になることです。特に新入社員・若手社員によく起きる次の課題・悩みに効果が期待できます。
・仕事を一人で抱え込んで、パンクする
・テレワークで、自分からコミュニケーションを取るのが苦手
・他者の力を借りるのが苦手で、上司・先輩側からフォローしないと仕事が進まない
・社内外の人に言われた事を、そのまま上司・先輩に伝えるだけの伝書鳩になっている
効果的な巻き込み力研修の実施によって、次の状態を目指せます。
| よくある新入社員・若手社員の課題・悩み | 新入社員・若手社員がよくある 課題・悩みを解決した後の姿 |
|---|---|
| 仕事を抱え込んで、パンクする | 周りに頼りながらも、助け合う |
| テレワークのため、自分からコミュニケーションを取るのが苦手 | よりよい仕事をするために、周りに遠慮せず自ら働きかける |
| 人の力を借りるのに抵抗感があり、いつまでたっても上司や先輩社員のフォローが必要になる | 上司・先輩社員の力を借りながらも、自らもよりよくなるための行動を行う |
| 顧客とのコミュニケーションや社内のPJでも、ただの伝書鳩になっている | 顧客・上司との共創・協働を大切にして、よりよくするための意識と行動がある |
このような変化をもたらすには、巻き込む意識とスキルの両面に働きかける研修であることが必要です。次の章で巻き込み力を効果的に促す研修内容について説明します。
2)巻き込み力研修の具体的な内容
巻き込み力を高めるには、意識とスキルの両面にアプローチすることが重要です。
意識とは、「巻き込むことが成果につながる」実感を持つことです。
スキルとは、「分かりやすいコミュニケーション」や「相手を動かすための具体的な働きかけの方法」などを指します。
この2つをバランスよく研修で身につけることで、現場に戻ってから巻き込み力を効果的に発揮できるようになります。
例えばアーティエンスの巻き込み力研修では、意識とスキルの両方にアプローチするために、シミュレーションワークを実施しています。
顧客から新サービスの受注を勝ち取る商談シミュレーションをチーム戦で行います。上司役・顧客役の講師と何度も報連相や商談を行い、巻き込み方と巻き込むことの重要性を体感します。
実践する中で、自分の考えを簡潔かつ分かりやすく伝える練習を重ね、相手に協力してもらうための伝え方を実践的に学びます。
また、関わる人から積極的に情報を引き出したり、質問や助けを求めることで、アウトプットの質が向上することを実感します。これにより、「周囲を巻き込むことが成果につながる」という意識が自然と育まれます。
意識とスキルの両方にアプローチできる巻き込み力研修を実施することで、社員が自ら動き、周囲を巻き込んで成果を生み出す力を身につけることが可能です。
3)【事例】巻き込み力研修を通じて得られたポジティブな変化
巻き込み力研修によって、ポジティブな変化が生まれた3つの事例を紹介します。
1)配属前研修で健全な不安を育み、積極性を引き出した新入社員育成事例
2)“自分だけ”から“みんなで”へー新入社員の意識変革が起きた事例
3)受け身姿勢を打破し、自発的な行動を引き出した若手社員育成事例
1)配属前研修で健全な不安を育み、積極性を引き出した新入社員育成事例
大手IT企業(5,000名程度)に対して、新入社員の6月末の配属前に実施した事例です。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 業種 | ITサービスの保守運用 |
| 企業規模 | 5,000名程度 |
| 実施時期・方法 | 6月末2日間。講師派遣型研修 |
| 課題 | 新入社員が配属後に上司を上手く巻き込めず、自信を失うケースが増加 |
| 結果 | 巻き込み力が上がり、多くの現場社員から「積極性がある」と高評価をもらう。 |
課題:配属後のギャップと離職率の高さ
新入社員研修を人事が丁寧に実施していましたが、配属後にギャップを感じ、自信を失うケースが多く見られました。半年後のフォロー研修では暗い表情の新入社員が目立ち、離職率も他のグループ会社に比べて高いことが課題となっていました。
以前、配属前に現場の厳しさを伝える研修を行ったものの、新入社員が萎縮し不満の声が上がったため中止。しかし、現場のリアルな厳しさを伝えることも必要だと考え、適切な方法を模索していました。
対策:配属前に巻き込み力研修を導入
配属前の6月末に2日間の巻き込み力研修を実施。実際の業務に近いシミュレーションを通じて、上司や顧客とのやり取りを体験しました。
研修を進める中で、新入社員は「良い仕事をするにはどう巻き込むか」を主体的に考えるようになり、2日目には巻き込み方で成功・失敗体験を振り返りながら、現場での活かし方を整理しました。
結果:積極性の向上と早期活躍
研修後、現場の管理職からは、「今年の新入社員は積極性がある」「率先して先輩社員の手伝いをしている」「お客様からサンクスメールをもらった新入社員もいる」といったポジティブな声が寄せられました。
人材開発チームも「ただキラキラした期待感を持つのではなく、現場の厳しさを理解しつつ、それでも挑戦しようとする健全な不安を持てる状態になった」と手応えを感じていました。
結果として、新入社員の主体性が高まり、配属後の適応力向上にもつながりました。
2)“自分だけ”から“みんなで”へー新入社員の意識変革が起きた事例
出版社(100名程度)に対して、新入社員のオンボーディング支援として実施した事例です。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 業種 | 出版社 |
| 企業規模 | 100名程度 |
| 実施時期・方法 | 5月中旬1日間。公開講座 |
| 課題 | 上司の教育方法と業務の多さに疲弊 |
| 結果 | 上司や先輩と共に成果を出す意識が強化。「上司と共に良い仕事をするのが最高」との声があがる。 |
課題:上司の教育方法と業務の多さに疲弊
出版社の新入社員は、非常に優秀で志望度が高い一方、現場での「背中を見て学べ」という伝統的な習慣や業務進行方法に戸惑い、立ち上がりが遅れることが課題となっていました。
また、現場の業務量に追われる中で、新入社員への教育が十分に行き届かず、ギャップ(リアリティショック)を感じる新入社員も多く、早期に効果的な支援を行う必要がありました。
対策:巻き込み力研修による意識改革
6月に行われる書店実習の前に、新入社員に巻き込み力研修を実施しました。研修では、新入社員が自分の意見を主張するだけでなく、上司や顧客の期待に応えつつ、どのように自分たちの考えを伝え、協力を得るかを学びました。
フィードバックを通じて視点を広げ、具体的な働きかけを実践することで、より良い仕事を作るための意識を養うことができました。
結果:協働意識の向上と積極的な行動
研修を受けた新入社員は、「自分がいいと思うものを、説得するだけではだめだと気づいた」との感想を述べ、上司や先輩と共に成果を出す意識が強まりました。
配属後、新入社員は「仕事が楽しい。厳しい時もあるが、上司と一緒に良い仕事をするのが最高だ」と感じ、積極的に業務に取り組んでいる様子が報告されました。人事責任者からは、上司との協力によって仕事の質が向上したとの声もあり、研修が効果を上げたことが確認されました。
3)受け身姿勢を打破し、自発的な行動を引き出した若手社員育成事例
中堅IT企業(1,000名程度)の若手社員を対象に、受け身姿勢を解消するためのフォロー研修として実施した事例です。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 業種 | SIer |
| 企業規模 | 1,000名程度 |
| 実施時期・方法 | 3年目社員に対して9月2日間。派遣型研修 |
| 課題 | 受け身姿勢と高い離職率 |
| 結果 | 会議での自発的な発言の増加と行動変化 |
課題:受け身姿勢と高い離職率
この企業の課題は、若手社員の受け身姿勢と高い離職率にありました。社員は「言われたことしかしない」といった状況で、管理職からは「使えない」との指摘があり、経営陣からは離職率を下げることが求められていました。
対策:対話を通じて認識を深め、巻き込み力を育成
研修当日、受講した若手社員は皆おとなしく、覇気のない状態で、シミュレーションワークでも自発的な行動が見られませんでした。
研修を進める中で、参加者たちの意欲の低さが明らかになったため、プログラムを途中で変更し、まずは社員一人ひとりの想いや感情を引き出す対話を行いました。
すると、社員から「会社を辞めたい」「研修は意味がない」「上司は無関心」といった本音が出てきました。この瞬間に、3年目社員が自身の課題と組織の問題に気づき、巻き込み力研修で得た気づきを現場にどう活かすかを話し合いました。
特に、ある受講生が「自分たちの取り組み姿勢が問題だ」と発言し、社員全体の意識が変化しました。
結果:自発的な発言と行動変容
研修後、最もおとなしかった女性社員が「私は変わりたい」と声を震わせながら発表し、自身の成長への意欲を示しました。これがきっかけとなり、彼女の上司からは「会議で発言したことがなかった○○さんが、発言してくれた」との驚きの声が上がりました。
また、研修を通じて人事と若手社員との繋がりが強化され、社員から悩み相談が増え、退職を考えていた社員も自ら相談をするようになりました。
3つの事例のように、アーティエンスの巻き込み力研修はさまざまな状況にあわせて実施できるため、それぞれの企業で抱えている課題の解決につながります。
4) 巻き込み力研修の効果を高める3つのポイント
巻き込み力研修の効果を高めるポイントは下記の3点です。
・周囲の環境が変わるタイミングで実施
・シミュレーションワークの世界観の徹底
・現場を意識した講師からのフィードバック
具体的に説明します。
1)周囲の環境が変わるタイミングで実施
巻き込み力研修は、節目となるタイミングで実施することをおすすめします。配属直前や半年後のフォロー研修などのタイミングで実施することで、次のステージに進むための意識を育みやすくなります。
節目以外に実施をする際は、なぜそのタイミングで研修を受けるのかを受講生にしっかり伝えることが大切です。
2)シミュレーションワークの世界観の徹底
巻き込み力研修において、シミュレーションワークを効果的に行うためには、研修の世界観を徹底的に作り込むことが大切です。受講生がその世界観に没頭できなければ、モチベーションが低下し、学びが半減してしまうためです。
例えば、講師に上司役・顧客役がいる場合にその2人が話していると、世界観が崩れ、受講生の熱量が一気に下がってしまいます。
このようなことが起きないよう、研修全体の雰囲気を整えることが重要です。
3)現場を意識した講師からのフィードバック
巻き込み力研修でのフィードバックは、ただ的確であるだけでなく、現場でも実際に起こり得る内容である必要があります。適切でないフィードバックでは学びが生まれませんし、現場で起こり得る内容でないと、受講生が素直に受け入れられません。
研修ワークを通して、現場で起こり得るフィードバックを意識し、受講生に実際の仕事に活かせるアドバイスを提供することが求められます。
しかし、現場を意識しすぎると、研修の内容とのつじつまがが合わずに受講生が迷ってしまうこともあります。また、適切なフィードバックをしようとしすぎて、カンペを読むような形式になり、受講生が自分に言われているように感じなくなることもあります。
研修と実務をつなげるフィードバックができるかが、効果的な学びを引き出すポイントです。
5)まとめ ~巻き込み力研修を実施するならアーティエンス~
本コラムでは、巻き込み力研修について説明しました。
巻き込み力研修は、社員が主体的に行動し、周囲と協力して成果を出す力を育むために不可欠な研修です。
意識とスキルの両面を強化することで、特に新入社員や若手社員は自信を持って仕事に取り組み、チームや組織に貢献することができます。
アーティエンスの巻き込み力研修は、意識とスキルの両面を強化できることはもちろん、時代にあわせて、より今の新入社員・若手社員の巻き込み力を高める内容にアップデートをし続けています。
当社の巻き込み力研修にご興味をお持ちいただけましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。貴社にぴったりなアプローチを一緒に考えさせていただきます。
若手・新入社員が受け身姿勢から脱却し、成果を最大化させるために、巻き込み力研修を効果的に活用しましょう。