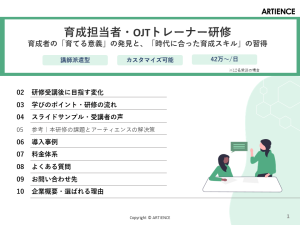- [ 研修・セミナーレポート ]
2023年5月16日_OJTトレーナー研修ー公開講座研修レポート
- 本内容は、2023年5月16日に開催された「OJTトレーナー研修」の公開講座研修レポートです。(参加企業数:3社、参加人数:18名、5グループ、オンライン1クラス)1)研修概要研修目的・学びのポイントと、当日のアジェンダ当日のアジェンダ1.
- 詳細を見る
【OJT研修】効果を高めるための目的・内容・進め方
更新日: ー
作成日:2022.12.21

「OJT研修って、結局何をやればいいのだろう?」
「新入社員に対するOJTがうまくいっていないなぁ」
「OJT研修と言う名の放置になっている。どんな内容が適切なんだろう」
新入社員の育成を担当する方々はよくこういった思いを持つのではないでしょうか。
人事として、
・毎年頑張って優秀な人材を採用している
・新入社員研修も様々なものを検討した上で、少しでも良いものを実施している
・研修終了日には、ある程度自信をもって現場に送り出す
という方が多いと思います。
しかし数ヶ月後、「え、彼が?」「え、彼女が?」といった人材が離職したことを知ったり、フォロー研修で新入社員に会ってみると
「あれ、もう少し積極的だったと思うんだけど・・・」
「あれ?思いのほか成長してないな・・・」
などのような感想を持つこともあるのではないでしょうか。
素晴らしい人材を採用し、しっかり研修を実施しても、「現場で活躍できない」「やる気が無くなり、退職してしまう」という状況になると、とても残念で悲しくなります。
そのような状況を少しでも改善していくために、本コラムでは、効果的なOJT研修を現場が実施できる内容を提示します。
最後までお読みいただくことで、現場で効果的にOJT研修を実施していくイメージを持ち、OJT研修の重要なポイントを理解できる内容になっています。
1)OJT研修の効果を高めるために実施すべき内容とは

OJT研修とは「実践をしながらの教育(On-the-Job Training)」のことです。日本企業においては最も多く実施されている人材育成の形式です。
日本の企業では、高校や大学等を卒業すると同時に企業に社会人としての基本やビジネススキルをあまり持たない状態で入社していく形が一般的です。そのため、企業に入社した新入社員は、入社後のOJT研修によって、社会人としてまたその企業にとって必要な人材として、現場で先輩や上司、OJTトレーナーといった教育担当者によって教育を受けながら成長していくのです。
本章では、OJT研修の内容をより理解・イメージするために、下記内容をお伝えしていきます。
・効果的なOJT研修の実施内容
・OJT研修を効果的にするOJTトレーナー研修の内容
効果的なOJT研修の実施内容
効果的なOJT研修の実施内容として、「OJT研修の体制構築し、整える」と「OJT研修は、計画・実行・振り返りの対応が必要である」の2つがあります。
それぞれ説明していきます。
OJT研修の体制構築し、整える
「OJT研修の体制構築し、整える」では、下記2つを抑える必要があります。
・教育の軸としてOJTトレーナーを設定する
・組織としての受け入れ態勢の構築を行う
それぞれ説明していきます。
教育の軸としてOJTトレーナーを設定する
OJT研修を効果的に実施するためには、新入社員を教育していく中心となる軸を設定することが重要です。そのために中心となる軸として、OJTトレーナーを設定し、OJTトレーナーとして教育していくことが必要となります。特に、OJTトレーナーが軸として機能するための組織からの働きかけとして、OIJTトレーナー研修を実施していくことが大切です。
組織としての受け入れ態勢の構築を行う
新入社員を教育していく軸として、OJTトレーナーの設定に加え、組織としての受け入れ態勢の構築が重要です。OJTトレーナーに任せきりにしてしまうと、OJTトレーナー自身の負担が大きくなりすぎたり、OJT教育がうまくいっていない時に適切に介入することができなくなります。そのためOJTトレーナーを中心にするものの、組織全体で新入社員を受け入れ、教育していくことが大切です。
OJT研修は、計画・実行・振り返りの対応が必要である
「OJT研修の計画・実行・振り返りに分けて扱う」では、下記3つを抑える必要があります。
・新入社員の育成方針の策定(計画)
・適切な業務機会の提供(実行)
・振り返り面談の実施(振り返り)
それぞれ説明していきます。
新入社員の育成方針の策定
新入社員を育成する上で、何を目指してどういうことを学んでいくかを明確にしていくことが重要です。現場で新入社員を育成しようとすると、現場の忙しい状況や日々起きる出来事に左右されて新入社員の教育が偏ってしまいます。そのため、OJT研修の開始時に育成方針を策定していくことが大切です。
具体的には
・目標設定の策定:OJT研修終了時にどのような状態になっていると良いのか(能力や考え方など)
・育成計画の立案:何をどの順番で学んでいくのか(マナー・スタンス・業務スキルなど)
・トレーナーや管理職との面談などのコミュニケーションルールの策定:いつどのタイミングでミーティングなどの機会を持つのか(毎日10分トレーナーと振り返り面談を行うなど)
などを、管理職、トレーナー、新入社員の3者で話し合い、合意しながら進めていきます。
適切な業務機会の提供
新入社員を育成していく上で、各々に合わせた業務をアサインし、業務機会を提供していくことが重要です。新入社員は、それぞれの能力や状態に違いがあり、各々に合わせたアサインが必要になります。少なすぎたり求められるレベルが低すぎると、新入社員の成長実感が損なわれ、モチベーションダウンに繋がります。逆に多すぎたり求められるレベルが高すぎると、新入社員は疲弊してしまい、精神疾患などの問題になる場合もあるからです。 具体的には、新入社員の育成方針の策定を丁寧に行っていくことと随時見直していくことです。
育成方針を一方的に決めつけるのではなく、新入社員にも自分のことを話してもらいながら合意を創っていきます。また、実際に実施してみると、想像して決めたこととは違うことが多々ありますので、随時見直すことで適切な業務機会の提供ができるようになります。
振り返り面談の実施
新入社員を育成していく上で振り返りを行っていくことが重要です。振り返りをすることで現状の把握や、目標との差異がわかるからです。また、振り返り面談の中で、新入社員の精神的な状態のリスクを把握することなども実施することができます。
具体的に振り返り面談で実施することとして
・現状の共有(できていること・もう少ししたかったこと)
・目標の確認(差異の確認や目標の見直しの必要性を話し合う)
・今後の行動の決定(具体的に行うことを明確にする)
・支援の提示(管理職やトレーナーなど周囲のメンバーからの必要な支援を確認する)
・新入社員のリスクの確認(睡眠や食欲など状態の把握を行う)
OJT研修の内容として「OJT研修の体制構築し、整える」と「OJT研修は、計画・実行・振り返りの対応が必要である」をお伝えしました。OJTトレーナーという教育の軸を作りながらも組織として関わり、新入社員と合意を取りながら進めていくことをOJT研修の内容で押さえておく必要があります。
OJT研修を効果的にするOJTトレーナー研修の内容
OJT研修を効果的にするOJTトレーナー研修の内容は、3つのポイントがあります。
・「OJT研修はなぜ大切か?」を伝える
・「OJT研修で行うことは何か?」を伝える
・「OJT研修で活用する知識や技術はどのようなものか」を伝える
それぞれ説明していきます。
ポイント①:「OJT研修はなぜ大切か?」を伝える
OJTトレーナーに新入社員に対して関わることの必要性と重要性を伝え、認識してもらうことです。
なぜなら、必要性と重要性をOJTトレーナーが認識することによって、優先順位の高い業務として新入社員教育を扱うようになるからです。必要性と重要性を認識していないOJTトレーナーは、日々忙しい中で新入社員と関わることを怠ってしまうことになり、新入社員が放置されることに繋がります。
具体的には下記の項目を扱います。
・OJT研修の必要性と重要性
・OJT研修を行うメリット(会社にとって、新入社員にとって、自分にとって)
・OJT研修を怠ることのリスク
・OJTトレーナーの役割など
ポイント②:OJT研修で行うことは何か?
OJTトレーナーが新人に対して何をすると良いのかを理解してもらうことです。
なぜなら、具体的な行動を理解することで、新入社員教育に必要な要素を網羅することができるからです。OJTトレーナーが具体的に行うことを理解していないと、当てずっぽうな場当たり的な教育が新入社員に対して行われることになり、自分の経験のみで新入社員に必要だろうと思うことを教えてしまうリスクがあります。また、具体的に提示することで、初めてOJTトレーナーを担当する人の不安を解消する目的もあります。
具体的には下記の項目を扱います。
・新入社員の目標設定の策定
・新入社員の育成計画の立案
・新入社員との面談など日々のコミュニケーションルールの策定
・関係性の構築
・周囲の協力体制の構築など
ポイント③:OJT研修で活用する知識や技術はどのようなものか
OJTトレーナーがOJT研修を実施する際にどのような指導を行っていけば良いかを理解してもらうことです。
知識や技術を持つことで新入社員に効果的な関わりができるようになります。OJTトレーナーが知識や技術が不足していると、行うことがわかっていても効果は出ない可能性が高まるからです。
具体的には下記の項目を扱います。
・ティーチング
・フィードバック
・コーチング
・周囲に依頼をするコミュニケーション方法など
このように3つのポイントを押さえることで効果的なOJTトレーナー研修を実施することができます。
2)OJT研修は「人が育つ組織をつくり、育むこと」を目的とすべき

第1章でOJT研修の内容について3つのポイントを押さえることはもちろん重要性をお伝えしました。第2章では、OJT研修の内容上に重要なのはOJT研修を実施する目的についてお伝えします。
OJT研修の目的を、「新入社員を育成するため」だけではなく、「人が育つ組織をつくり、育むこと」に設定していくことが重要です。
新入社員を育成するためだけを目的にしてしまうと、「新入社員のため」が最優先され、新入社員のためにOJTトレーナーが負担を負う状況になってしまったりします。また、人が育つ組織をつくり育むことを目的にすることで、全員が新入社員を含む育成に対して責任を持ち、育成に対して積極的に関わることができる組織を醸成することができるからです。
OJT研修の内容によって人が育つ組織をつくり、育むための3つのポイント
OJT研修の内容によって人が育つ組織をつくり、育むための3つのポイントは、下記になります。
・OJT研修が新入社員・トレーナー双方にとって良い経験となるための設計を行う
・管理職・トレーナー・新入社員の3者構造をつくる
・組織全体が新入社員に関わる状態をつくる
上記内容を、それぞれ説明していきます。
OJT研修が新入社員・トレーナー双方にとって良い経験となるための設計を行う
新入社員にとって良い経験となるのは当然ですが、トレーナーにとってもOJTトレーナーという役割が良い体験になることが大事です。
なぜなら、トレーナーとして良い体験をすることで、「人を育成すること」「後輩と関わること」に対してポジティブな感覚を持つことができることで、組織全体での育成に積極的になったり、育成をするということに肯定的な態度をもつ人材を増やすことができるからです。
具体的には、トレーナーに対して、「育成に対して肯定的な感情を醸成すること」と「育成に対して否定的な感情を解消すること」が重要です。
育成に対して肯定的な感情を醸成すること
トレーナーという役割を担うことで、新しい技術などを学ぶことや成長できることが実感できるような研修や振り返りの機会を提供することで「トレーナーをやってよかった」といった感覚を持ってもらうようにすることです。
そのために、OJTトレーナー研修では、OJT研修を行うメリットにおいて、トレーナー自身にとってのメリットを強調し、実感を持ってもらうことが必要になります。
育成に対して否定的な感情を解消すること
トレーナーという役割を担うことで、業務負担が増え、自分の業務が逼迫したり、残業が増えたりしてしまうと「トレーナーをやらなければよかった」といった感覚を持ってしまい、育成に対しての否定的な感情になりやすくなります。
そのために、OJTトレーナー研修では、OJTトレーナーの役割において、OJTトレーナーの役割は「新入社員教育の全責任を負う」のではなく「新入社員教育の中心人物であり、他のメンバーに協力を依頼する人」であると提示することが必要になります。
管理職・トレーナー・新入社員の3者構造をつくる
管理職・トレーナー・新入社員の3者が関わり合う設計にすることで、OJTトレーナーに丸投げせず、管理職が関わり、組織として新入社員育成に責任を持つ体制にすることが大事です。
なぜなら、OJTトレーナーという新入社員育成の担当者が任命されてしまうと、「担当者任せ」になりやすいからです。また、3者構造にすることで、もしトレーナーか新入社員のどちらかが、相手に対して問題を感じた時やもしくは双方とも問題を感じている時に3人目として関わることによって、問題を解決しやすい環境を創ることができます。
具体的には3者構造として実施することとして
・新入社員の目標設定の策定
・新入社員の育成計画の立案
・新入社員との面談など日々のコミュニケーションルールの策定
上記3項目を管理職も含めた3人で実施します。そうすることで、新入社員育成の方向性や育成の方針などの合意形成を行うことができます。また、1ヶ月に一度管理職とトレーナーで面談を行うことで、トレーナーの新入社員育成の悩みを解決したり、トレーナーがトレーナーとして成長していく支援を行うことも効果的です。
OJTトレーナー研修では、研修の事後課題として管理職との面談を用意しておくこと、また管理職に人事部など企画側からの依頼を丁寧に行っておくことが大切です。
③ 組織全体が新入社員に関わる状態をつくる
組織全体が新入社員に関わる状態をつくるとは、新入社員を迎え入れる組織のメンバー全員に、トレーナーに新入社員育成を丸投げせず全員で関わることを明示します。トレーナーからの新入社員対応の依頼を積極的に受け入れることを管理職や会社から要請することです。
トレーナーが新入社員対応を依頼した時に、周囲が積極的に応える環境がないと、トレーナーが適切に周囲の協力を得ることができず、トレーナーが孤立感を感じてしまうことや、高い業務負担によって疲弊してしまう可能性があるからです。また、こういった要請を通じて、会社として「新入社員を育てるのは組織全体の仕事である」といったメッセージを伝え、人が育つ組織をつくるというOJT研修の目的がメンバー全員が認識する状態をつくることが大切です。
具体的にチーム体制をつくる方法として、管理職かトレーナーが組織のメンバーと新入社員が関わる場を設定する方法があります。
管理職が組織のメンバーに協力依頼を行った上で、トレーナーが新入社員と一緒に各メンバーと話をする機会をセッティングし、関わる頻度を上げていくことによって新入社員と組織のメンバーそれぞれの関係性を構築していくことができます。また、新入社員がチーム会議などで自分の1ヶ月の成果を発表するなど、組織のメンバーが新入社員の状況や状態を把握する場をつくることも効果的です。
OJTトレーナー研修では、周囲の協力体制の構築において具体的に誰に何を依頼するかをイメージする時間を取ることや、周囲に依頼をするコミュニケーション方法を練習しておくことで、トレーナーが行動しやすいようにしておくことが大切です。
このように、第1章で提示したOJT研修の内容は、第2章で提示した「人が育つ組織をつくり、育むことを目的にする」を反映した形でトレーナーに対して実施していくことをお勧めします。そうすることで、OJTトレーナーを中心にした人が育つ組織をつくるためのOJT研修が実施できるようになるのです。
3)OJT研修実施時に発生しやすいQ&A
この章では、筆者が研修開発に関わるときや講師として関わるときによく受ける質問に答えることで、より効果的にOJT研修を実施するヒントを提示していきます。
Q1:OJTトレーナー研修を実施するタイミングや回数はどうすると良いのか?
タイミングは、新入社員の対応が必要になったタイミングで実施することと、そのタイミングに応じた回数で実施することです。新入社員の対応が必要になったタイミングというのは、トレーナーが最も研修を必要としている時であり、またトレーナーとして行動を振り返る時でもあるからです。
具体的には下記のようなタイミングと回数で実施している企業(新卒採用の場合)があります。
・1回目:4月から5月ごろ「新入社員が現場に配属される少し前」です。
理想としては、配属2週間前くらいに実施すると、トレーナーが研修を受講することで新入社員を受け入れる準備が整い、また周囲への依頼などを整理する時間を取ることもできます。
・2回目:9月から10月ごろ「新入社員が一通りの業務を覚え、一部1人で行うようになってきた時期」です。
これまで、ティーチングを中心に初めての業務を覚えていく時期から段々とコーチングに移行して新入社員を観察しながら支援的に関わる場面が増える時期に、途中経過としての振り返りや今後の対策、コーチングの技術の再確認などを行います。
・3回目:2月から3月ごろ「新入社員が2年目になり、トレーナー業務が終了になる時期」です。
新入社員が1年目が終了する時期に、2年目に向けて積み残しがないかを確認し、最後の関わりを考えていくことを行うことや、トレーナー自身が、自分にとってよかったことやトレーナー活動で成長したことを振り返り、トレーナーという役割を良い体験だったと感じることができるようにしていきます。
新入社員の対応が必要になったタイミングは、企業によって違いがありますので、設計時に検討していくことが必要になります。
Q2:OJTトレーナーに任命する人選はどのようにすると良いのか?(年次や、向いている人向いていない人など、どのように考えると良いか)
基本的には、OJTトレーナーとして成長してほしい人を任命することが大切です。
なぜなら、OJTトレーナーは人が育つ組織をつくり育むための一環として任命すると考えるからです。そう考えると、人が育つ組織をつくり育むといったことを理解し、実行できる人材育成としてOJTトレーナーを任命することが大切になります。
年次で考えると、これも企業によって違いますが、人材育成に関わり始めてほしい年次となります。私が関わってきた企業の傾向でみると、早ければ2年目や3年目くらいから任命しています。ただ、2年目3年目の方ですと、自分の業務のコントロールがまだ未熟だったり、教えるということへの自信の無さがあり、苦労しているケースによく出会います。若い年次に任せる場合は、その分サポート体制を整備することが大切です。
向いていない人を任命して良いのか?ということに関しては、基本的には任命する優先順位を下げて良いです。なぜなら、新入社員への影響が大きいからです。やはり新人が1年間、企業によっては2年、3年と最も関わる人物となりますので、その影響を鑑みて適切な人材を任命することが妥当です。ただ、向いていないけれども「どうしてもこの人にOJTトレーナーの役割で成長してほしい」という場合は、新入社員は誰と組ませるのか、サポート体制はどうするのかを十分検討していただきたいです。
Q3:「メンター制度」を同時に立ち上げたほうが良いのか?そのメリットデメリットは?
可能であれば「メンター制度」を同時に立ち上げることをお勧めします。
なぜなら、OJTトレーナーと新入社員は、上下の関係にならざるを得ないため、新入社員からすると悩みを打ち明けづらい状況になりやすいためです。そのため、「メンター」という「気軽に相談できる人」を役割としておくことは、新入社員に対して効果的な制度です。
※「メンター制度」は、日本の企業では主に「気軽に相談できる先輩」といった意味で使われていることが多くありますので、その使い方を元に書いています。
メンター制度をおくメリットは上記に記載した通り、トレーナーに相談しづらいことを話せる相手がいるため、新入社員のサポートが充実することです。また、OJTトレーナーに比べると、年次が低くても任命しやすいために早期に人材育成の経験をさせたい場合などに有効です。
デメリットはそれだけ人数が必要になることです。毎年トレーナーとメンターを任命していき、新入社員の対応をしていくことは、かけているマンパワーが大きくなります。そういった時はメンターという役割をおかず、組織の他のメンバーの巻き込みを強化することで対応することも可能です。
メンターに関して詳しく知りたい方は、下記コラムを参考にしてください。
新入社員にメンターをつけることで組織への安心感をもたらし、成長を促す
Q4:OJTトレーナーの負担が多くなるので、OJTトレーナーになることを嫌がることへの対応策は?
第2章「OJT研修の目的は、『人が育つ組織をつくり、育むこと』にするべき」でお伝えした通り、基本的には「OJT研修が新入社員・トレーナー双方にとって良い経験となるための設計を行う」ことが大切です。
その上で下記の対応をお勧めします。
・上司からOJTトレーナーの任命理由を丁寧に伝える(期待を込めて)
・業務負担の軽減やサポート体制による負担の軽減を提示する
・目標設定に組み込むなどOJTトレーナーの業務が評価されるようにする
こういったことをしていくことで、OJTトレーナーに対しての肯定的な感情を醸成していきます。
Q5:OJTトレーナーと新入社員の相性が悪いときはどうしたらいいか?
相性が悪いことは問題ではないのですが、新入社員に悪影響が出た時には介入をすることが大切です。OJTトレーナーと新入社員に限らず相性が悪いことは、どのような場面でもあり得ます。そういった時にどのように対応するかがビジネスパーソンとしてもOJTトレーナーとしても成長する機会になります。
OJTトレーナーにとっては、自分と相性が悪い相手だとしても、成長させるために何ができるかを考え実践してもらうことや、新入社員にとっては、自分と相性が悪い相手に対してどのように受け止め、どのように接していくかを学んでもらう機会にしてもらうことが大切です。
ただ、新入社員に悪い影響が出てきてしまい、問題が悪化してきしまった時には交代などの対応も準備してくことが必要になります。このままいくと乗り越えられないかもしれない時には、一旦無理せず、その課題を取り下げることが必要だからです。
具体的には
・新入社員が深く悩んでしまい、日常の業務に支障をきたし始めている
・何らか精神疾患などの兆候が見られる
・実質的にOJTトレーナー制度が行われなくなっているなど
こういった状況が出てきてしまい、改善が難しい場合にはOJTトレーナーの交代も必要になります。
4)まとめ
本コラムでは、OJT研修の内容に関して、お伝えいたしました。
具体的には、下記内容です。
・OJT研修の効果を高めるための実施内容と、3つのポイント
・OJT研修の目的は、「人が育つ組織をつくり、育むこと」にするべき
ということです。
今回の記事を参考に自組織にとって最も効果的なOJT研修を構築してくださると嬉しいです。
私たちアーティエンスでは企業の方の特性や状態を元に制度設計から研修までを設計していきます。もしもっとより詳しく知りたい、一緒に考えてみたいと思った方はご相談ください。
本コラムが皆さんの助けになれば幸いです。