
- [ コラム ]
新入社員のメンタルヘルス|3段階の予防と不調のサインを知って早期に対応を
- ・最近、特に新入社員がメンタルヘルスが原因で休職することが増えた…・新入社員のメンタルヘルス、組織としてどのように取り組めばよいのだろう…といったお悩みをお伺いすることが多くなりました。メンタルヘルスが不調になる原因は、人によってさまざまで
- 詳細を見る
【管理職向けメンタルヘルス研修】に必要な6つの内容と注意点
更新日: ー
作成日:2023.3.27

「管理職向けのメンタルヘルス研修は、どのような内容が良いのか?」
「精神疾患による休職が増えている。管理職にメンタルヘルス研修を受けさせたい」
「ストレスチェックが悪かった。管理職にメンタルヘルス研修を受けさせるのはどうだろうか」
筆者は、研修講師とカウンセラーの顔の2つをもっていることもあり、人事部の方に上記のような相談を受けることが数多くあります。
ただ何となく管理職向けのメンタルヘルス研修を行うと、失敗するケースが多いです。
「管理職の方にメンタルヘルス研修を効果的に実施することは、本当に難しい」
というのが私の考えです。なぜなら、管理職の方にとってメンタルヘルスという問題は普段求められている役割や能力と大きく異なるからです。
研修後の管理職によくあるケースとしては、
「興味を持てない」
→メンタル不調の当事者や関係者にならない限り身近な問題として捉えづらい
「理解できない」→精神疾患の名前など初めて聞く内容が多く、またそういった症状に接したことがないと想像できず理解がしづらい
「やれるように思えない」
→これまでの知識や経験では対応できないように思ってしまうため、実際にメンタルヘルスの問題が起きても適切に対応できるように思えない。また管理職の業務に加えてメンタルヘルス対応まで手が回らないように感じてしまう
といった状態となり、実際のマネジメントでの行動に反映されないということが起きます。
この記事では上記の状況を踏まえて、管理職が「興味を持ち」「理解しやすく」「やれるように思える」ために、必ず押さえてほしいメンタルヘルス研修の6つの内容や実施する際のポイント・注意点を提示します。
本コラムを参考に、管理職の方々に効果があるメンタルヘルス研修を実施していくイメージや検討していくべきことを明確にしていきましょう。
1)管理職へのメンタルヘルス研修で行うべき6つの内容

管理職にメンタルヘルス研修を行うのに必要な6つの内容があります。 この6つの内容全て扱うことがとても重要です。
なぜなら、6つの内容を扱わないと知識のインプットだけにとどまってしまうことや、前述の「興味を持ち」「理解しやすく」「やれるように思える」状態にならないために行動の変化に繋がらないため、研修の効果が出ないからです。
【管理職のメンタルヘルス研修で必要な6つの内容】
①管理職がメンタルヘルスを扱う必要性
②管理職によるラインケア
③主なメンタルヘルスの問題
④メンタルヘルス問題の発見と対策
⑤部下とのコミュニケーション
⑥管理職自身のメンタルヘルス
この6つの内容について扱う理由も合わせて、それぞれ説明していきます。
①管理職がメンタルヘルスを扱う必要性
管理職研修でメンタルヘルスを扱う時には、必要性を扱うことが最も重要です。
必要性を感じないと「興味を持つ」ことができず、自分事に捉えることができないからです。少なくとも以下の3つの内容は含まれている必要があります。
・役割として必要であること
・従業員への影響を持っていること
・部署への悪影響があること
役割として必要であること
管理職は、従業員の心の健康を守る役割を持っています。法令として「安全配慮義務」を管理職が担っているためです。また管理職は厚生労働省の定める「労働者の心の健康の保持増進のための指針」のなかで、ラインケアとしてメンタルヘルス推進の需要な役割として定義されています。
従業員への影響力を持っていること
管理職は、従業員への影響力を持っています。管理職が自分の部下に仕事を与えています。その仕事の量や質、与えられ方によっては、従業員が精神疾患になる原因にもなります。
例えば長時間労働や要求度が高い仕事、自由度が少ない仕事、周囲の支援が受けづらい仕事などは従業員がメンタル不調になる要因になります。管理職は、自分の仕事の与え方が部下のメンタル不調に影響を与えることを認識する必要があります。
部署への悪影響があること
メンタル不調が一度発生すると経営としても部署運営にも悪影響が大きくなります。
休職のサポートなどで代わりの人員の手当や急遽行う引継ぎなどと、人員が必要になれば経営への影響がありますし、そういった人の配置の変更や休職者のサポートの時間などがあれば部署運営に影響があります。時には、新しい人員を採用する必要性も出てくるでしょう。リソースも、コストもかかります。
そのため、今現在は問題がないとしても、発生した時の影響が大きいからこそ問題がないうちから対応していく必要がある、ということを認識してもらうことが大事です。このように、必要性を3つの点から研修で扱うことで管理職がメンタルヘルスに興味を持ち、自分事になるようにしていくことが重要です。
②管理職によるラインケア
管理職によるラインケアを扱うということは、管理職が「どこまでやると良いのか」という役割の範囲を提示することです。
厚生労働省が定めた「労働者の心の健康の保持増進のための指針」のなかに出てくる4つのケアの中の一つのこと
・労働者自身によるセルフケア
・管理監督者におけるラインケア
・事業場内の健康管理担当者による「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」
・事業場外の専門家による「事業場外資源によるケア」
※ラインとは、職場の管理監督者のこと(部署単位やプロジェクト単位で考える)を意味します
ラインケアという役割の範囲を知ることで、管理職はどこまでやれば良いのかが明確になるため「自分はここまでやればいいんだ。他は〇〇に任せれば良いんだ」といった安心感を持つことができます。そういった安心感が「やれるように思える」状態を作ることができるのです。
ラインケアとして扱う内容を2つご紹介します。
管理監督者による部下への接し方
管理監督者による部下への接し方は大きく3つあります。
・「いつもと違う」部下の把握と対応→それまで遅刻をしたことがなかった部下が遅刻を繰り返したりする、といったような今までの行動とは違う、という異変に気づき、対応をしていくことです。
・部下からの相談への対応→日常的に部下からの相談に対応することや、長時間労働等過労状態にある部下など特に個別の配慮が必要な部下に対して自分から声をかけ、傾聴・情報提供・産業医などへの受診の促しなどを行っていくことです。
・メンタル不調の部下の職場復帰への支援→休職後の職場復帰時の不安を受け止め、緊張を緩和していくことです。
職場環境等の改善を通じたストレスの軽減
アメリカ国立労働安全衛生研究所(NIOSH)が提示したストレス対策のポイントが参考になります。
②労働者の社会生活に合わせて勤務形態の配慮がなされていること
③仕事の役割や責任が明確であること
④仕事の将来や昇進・昇級の機会が明確であること
⑤職場でよい人間関係が保たれていること
⑥仕事の意義が明確にされ、やる気を刺激し、労働者の技術を活用するようにデザインされること
⑦職場での意志決定への参加の機会があること
③主なメンタルヘルスの問題
メンタルヘルスの問題として、発生しやすい精神疾患などの知識として備えてもらうことです。なぜなら、精神疾患などの知識があるからこそ、部下の状態の違和感に気づくことや、休職時の対応や復職時の対応ができるようになるからです。
特に、この内容を管理職の方からすると、初めて聞く用語も多いので、どれだけわかりやすく、身近な例を出しながら講師が伝えることができるかが、メンタルヘルスを「理解しやすく」するポイントです。具体的に押さえておくべきメンタルヘルスの問題を提示します。
・双極性障害
・統合失調症
・パニック障害・不安障害
・適応障害
・睡眠障害
・依存症(アルコール依存症など)
・発達障害
研修会社によっては、発達障害についてあまり触れないこともあるかもしれませんが、発達障害は企業の中でしばしば周囲から問題行動として見なされるケースが多いです。そのため評価が低い、他の従業員との人間関係の悪化などが起こることがあります。発達障害をお持ちの方がストレスを抱え精神疾患を発症することがあります。そのため、主なメンタルヘルスの問題の中に発達障害まで含めることをお勧めします。
④メンタルヘルス問題の発見と対策
ラインケアの項目で出てきました、管理監督者による部下への接し方の中の「いつもと違う」部下の把握と対応の具体的な方法を提示することです。
なぜなら、「いつもと違う」ことが必要だとわかっていても、実際にどのようにしていくと実行できるかを理解したり練習しないと現場では行動ができないからです。そのため、研修内で具体的な方法を練習しておく必要があります。
具体的には、「いつもと違う」部下の様子とはどのような状態かを提示します。
「いつもと違う」部下の様子の一例・遅刻、早退、欠勤が増える
・休みの連絡がない(無断欠勤がある)
・残業、休日出勤が不釣合いに増える
・仕事の能率が悪くなる。思考力・判断力が低下する
・業務の結果がなかなかでてこない
・報告や相談、職場での会話がなくなる(あるいはその逆)
・表情に活気がなく、動作にも元気がない(あるいはその逆)
・不自然な言動が目立つ
・ミスや事故が目立つ
・服装が乱れたり、衣服が不潔であったりする
また、「いつもと違う部下の様子」に気づいた時の対策を提示します。
「いつもと違う部下の様子」に気づいた時の対策・聞くこと
→部下の話を聞くこと。一方で勝手に判断せず状況把握に努めること
・繋げること
→産業医や医師に繋げること。企業によっては先にカウンセラーや保健師、看護師などにまずは繋げ、そこから産業医や医師に仲介していってもらうなど
⑤部下とのコミュニケーション
普段行っておくと良い部下とのコミュニケーションについて扱います。普段からの関係性があるからこそ部下は管理職に自分の状態を相談したり、安心して仕事をしていくことができるからです。具体的には、まず実行しやすいスキルとしてストロークは効果的です。
※ ストローク:相手に「私はあなたのことを気にしていますよ」というサインを投げかける行為です。人は認知されたい(知っていてほしい、気にかけて欲しい」という欲求を持っています。その欲求を満たすことで安心し、好意を持つのです。
・相手の顔をみて挨拶する
・メールにすぐに返信する
・声をかけられた時に振り向く(パソコンに顔を向けたまま振り向くのではなく)
・相談を聞く時はしっかりと相手に対する
・話を聞く時にうなづくなど反応をする
⑥管理職自身のメンタルヘルス
管理職自身がメンタル不調にならないようにセルフケアについて学ぶことです。管理職自身も強いストレスにさらされている存在であり、自分自身のケアをする必要が高いからです。
具体的なセルフケアとして、「自分の状態に気付くこと」と「4つのRの実践」をお勧めします。
自分の状態に気づくこと
・睡眠:よく寝れているか、寝つきが悪い、何度も目がさめるなど
・食事:美味しく食べることができているか、美味しいものを食べようなど食への興味があるかなど
・活動的か:以前やっていた趣味を全くしていない、する気になれないなど
4つのRの実践
・リラクゼーション(Relaxation)
自律神経をしっかりと休め、心と体のバランスを整えること
腹式呼吸、アロマセラピーなど
・レスト(Rest)
体をしっかり休めること
睡眠、マッサージなど
・レクリエーション(Recreation)
遊ぶ、楽しむ、笑うなど心身をリフレッシュすること
スポーツ、キャンプ、カラオケなど
・リトリート(Retreat)
非日常に身を置き、静養すること
旅行、森林浴など
また、管理職自身のメンタルヘルスに関しては、弊社コラム「管理職が潰れる4つの原因&3つの悪影響・潰さないための3つの対処法」にて記載しています。合わせてお読みいただけますとより深く理解できます。
ここまで管理職へのメンタルヘルス研修で行う6つの内容を提示しました。実施に研修を実施する時には、この6つの内容を念頭に置きながら、自社の管理職の状態に応じて、どの内容を厚めに扱うか、どういった伝え方をするかなどをよく検討することをお勧めします。
2)管理職のメンタルヘルス研修を実施する前にすべき準備
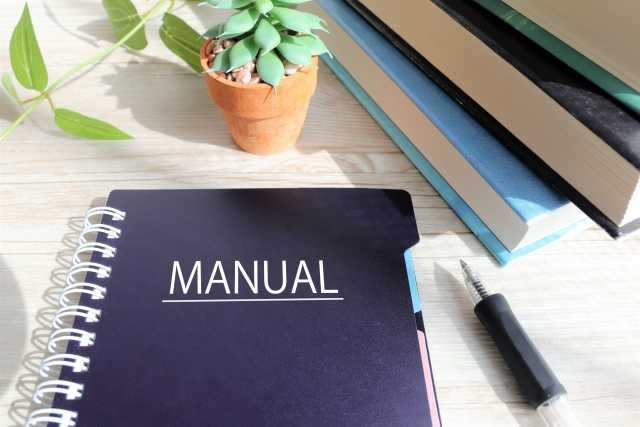
管理職のメンタルヘルス研修を実施するには、その前に十分な準備が必要です。メンタルヘルスという題材は管理職にとって身近なものではないため、興味関心を持つのが難しかったり、実践イメージが沸かないことがあるからです。
具体的には4つの準備をすることをお勧めします。
・管理職の仕事上の優先順位をあげてもらう仕掛けを用意する
・メンタルヘルスの問題に対して具体的なイメージを作る仕掛けを用意する
・管理職の不安を取り除く(メンタルヘルスという重い仕事を担うこと・自分にはよくわからない内容であるといった不安など)
・研修終了後の定着策をあらかじめ計画する
それぞれ説明していきます。
管理職の仕事上の優先順位をあげてもらう仕掛けを用意する
社長や役員など上位者の講演やメッセージを用意することで、「会社は本気にこの問題に取り組んでいる」と伝えること(難しい場合は、メールでのメッセージや動画などの対応でも可能です)や、管理職の上位者が個別に受講者に学んで欲しいことを提示することで上位者からの期待を体感するようにするなどです。
メンタルヘルスの問題に対して具体的なイメージを作る仕掛けを用意する
研修でただ知識を伝えるだけではなく、詳細なストーリーを含めた事例などを用意し、メンタルヘルスの問題はどのようなものかというイメージ作りを強化します。
例えば下記のようなストーリーなどを提示します。
・活動的で能力の高い5年目社員
・ポジティブな発言が多く周囲の評判も良い
・ただ最近遅刻はしないが、時間ギリギリに出勤することが増えている
・「大丈夫か?」と声をかけると「大丈夫です」と元気よく返事が返ってくる
・あまり注意を払っていなかったが、ある日急に出社しなくなった
・そのままほとんど連絡が取れず、休職後、退職となった。
このように、「ありそうだな」というシチュエーションを用意しておくことでイメージがしやすくなります。
管理職の不安を取り除く(メンタルヘルスという重い仕事を担うこと・自分にはよくわからない内容であるといった不安など)
4つのケアにおける他の3つのケアをあらかじめ制度として用意しておくこと、そしてそのことを管理職に説明します。そうすることで「まずは学んだことをやっていけばいいんだ」といった気持ちを醸成することが可能です。
また、ガイドブックや相談先(カウンセラーなど)を用意しておくことで「悩んだらここを見たり、相談して良いんだ」といった気持ちを醸成することも必要です。
研修終了後の定着策をあらかじめ計画する
メンタルヘルスという問題は、「対応可能だし、適切に対応すれば効果が出るんだ」といった実感を持ってもらうような仕掛けを行います。
例えばカウンセラーと連携して、研修終了後メンタル不調の可能性のある従業員を管理職から紹介してもらい、カウンセラーの面談による状態の安定化など実績を作っていけるようにするのもいいでしょう。
そうすることで管理職にカウンセラーなどによってメンタル不調の対応をすることは良いことだ、といった体験をしてもらえるようにしていくことが可能です。
3)管理職にメンタルヘルス研修を実施する際の注意点
管理職にメンタルヘルス研修を実施する際の2つの注意点をお伝えします。メンタルヘルスは人の心についての内容を扱うため、通常の研修とは違う注意を行う必要があります。
個人情報の扱い方には細心の注意を払うこと
メンタルヘルス研修を行い、その中でグループワークなどを行うとどうしても個人を特定できてしまうような会話になりやすくなります。
時には個人の精神疾患の状態などが話題にのぼってしまうことがあります。これはとても不適切な状況ですので、何度もアナウンスすることや、そういった個人情報が出ないようにケースを使うなど代替えの内容を用意しておく必要があります。
受講者にメンタル不調者がいる可能性を考慮すること
管理職の中には過去や現在においてメンタル不調の状態の方がいることがあります。そういった方々は研修の中で扱う内容によってはフラッシュバックが起きてしまうなど状態が悪化する可能性があります。
研修開始前に、精神疾患の既往歴がある方がいるかどうかを講師と共有し、言葉の使い方などを整理することが大事になります。
4)まとめ
本コラムでは、下記内容に関して、お伝えしました。
・管理職へのメンタルヘルス研修で行うべき6つの内容
・管理職のメンタルヘルス研修を実施する前にすべき準備
・管理職にメンタルヘルス研修を実施する際の注意点
本コラムを参考にしていただき、管理職へのメンタルヘルス研修によって、管理職の方がメンタルヘルスの理解を深め、従業員の心の健康を保ちながら高いパフォーマンスを発揮する組織を作っていただくために、今回のコラムを参考にしてくださると嬉しいです。
メンタルヘルスというマネジメント課題は、コラム内でも触れた通りマネジメントのなかで優先順位が下がりがちです。 しかしながら一度発生するとその影響が大きい、ということが特徴です。
私たちアーティエンスでは企業の方の特性や状態を元に制度設計から研修までを設計していきます。もしもっとより詳しく知りたい、一緒に考えてみたいと思った方はご相談ください。
本コラムが皆さんの助けになれば幸いです。
研修でお悩みの方へ
研修は、内容次第で成果が大きく変わります。もしも現在、自社の課題を解決できる最適な研修を探しているのであれば、アーティエンスまでご相談ください。
新入社員研修から管理職研修、組織開発まで、お客様の課題解決にこだわり、多くの実績を生み出してきたプロフェッショナルが、貴社の課題にあわせた最適なプランをご提案させていただきます。
参考:人事・労務担当者のための産業医紹介ナビ




