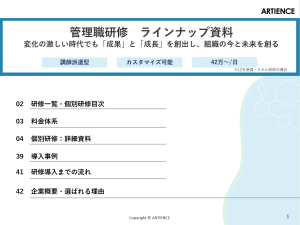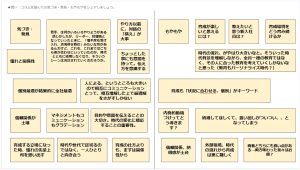-
[ コラム ]
メンバーの力を引き出す!管理職研修でリーダーシップを磨く方法
- 「管理職がチームをうまくまとめられず、仕事のスピードも質も落ちている…」「管理職の目標達成率が下がっている…」このような問題に直面し、管理職に対してリーダーシップ研修を実施する必要性を感じているのではないでしょうか。管理職のリーダーシップが
- 詳細を見る
【管理職候補者研修】視座を高め管理職としての挑戦と活躍を促す
更新日:
「管理職候補者研修ってやる意味あるのだろうか?」
「管理職候補向けの研修ってどんなことをすればいいの?」と疑問に感じる方も多いでしょう。
一般社員と管理職では求められる役割が大きく異なります。
管理職になったその日から、すぐに役割を全うできるわけではなく、むしろ適切な準備がないまま昇進すると、管理職自身が戸惑い、チームのパフォーマンスにも影響を及ぼしてしまうケースが多く見られます。
だからこそ、管理職になる前の入念な事前準備が必要です。その準備として有効な手段の一つが「管理職候補者研修」です。
本コラムでは、「管理職候補者向け研修」の効果や具体的な内容、実施時の注意ポイントを詳しく解説します。
管理職候補研修を通じて、未来のリーダーの成長を促し、組織全体のパフォーマンス向上につなげましょう。

大学卒業後、大手通信会社、アルー(株)勤務後、2010年にアーティエンス(株)を設立。業界歴17年。大手企業から、中小企業、ベンチャー企業の人材開発・組織開発の支援を行っている。専門分野は、組織開発、ファシリテーション。
目次
1. 管理職候補者向け研修で「チームの成果」への変化を促す
管理職候補研修を行う目的は、一般社員から管理職になるための準備として、「自分の成果を上げる」だけでなく、「チームの成果を最大化する」という視点を身につけてもらうことです。
一般社員時代は「自分自身の成果を重視する」ことが求められますが、管理職になると「チーム全体の成果を最大化する」という役割へと変わります。
この視点やスキルの転換を事前に学んでいないと、管理職になった際にうまく役割を果たせず、大きくつまずいてしまうリスクがあります。
そうならないためにも、管理職候補研修では、自組織の管理職に最も求められる役割に応じて、必要なスキルを強化することが一般的です。
例えば、チーム力が弱い組織では、チームビルディングや部下育成をテーマにした研修が効果的です。
また、管理職同士の連携が弱い組織では、情報の伝達や共有をスムーズにするための研修を行うのも良いでしょう。
どのような内容であっても、個人の視点にとどまらず、チーム全体の視点を持ち、チーム成果の最大化を意識できるよう促すことが重要です。
こうした視点を持つ管理職候補を育成することで、組織が期待する管理職の役割を果たせる人材を育てることができます。
2. 管理職候補研修の3つの効果
管理職候補者向けの研修には、以下の3つの効果があります。
・管理職になることへの前向きな感情を育む
・昇進後、管理職業務へスムーズに移行できる
・事業戦略を推進できる組織創りが進む
それぞれの効果について、詳しく説明します。
2-1. 管理職になることへの前向きな感情を育む
管理職候補研修によって、「管理職になること」に対して前向きな感情を持てるように促します。
近年、管理職にネガティブな印象を持つ人が増えており、「責任が重い」「プレイヤーとしての仕事ができなくなる」といった不安から、管理職への昇進を避けたいと考える社員も少なくありません。
十分な準備や心構えがないまま昇進すると、モチベーションが低下しやすくなり、結果的に管理職としての役割に消極的になってしまいます。
特に、管理職の魅力ややりがいを知る機会がないまま昇進すると、「やらされている」という意識が強くなり、主体的に行動したり、成長意欲を持ったりすることが難しくなります。
だからこそ、管理職候補研修を通じて、管理職という役割の価値や意義を理解し、前向きな感情を育むことが重要です。
研修の中で「管理職として働くことが自分のキャリアにどのような意味を持つのか」を考える時間を設けることで、不安を軽減し、次のステップへと前向きに進むことができるようになります。
「管理職になることは、自分の成長やキャリアにとって大きなプラスになる」と捉えられれば、学びやチャレンジに対する意欲が高まり、管理職としての成長スピードも加速します。
さらに、管理職が前向きに役割へ向き合う姿勢は、チームや部下にも下記のような良い影響を与えます。
・管理職が自信と意欲を持って役割に向き合うことで、チームにも前向きな姿勢が伝わる
・管理職が自身の成長を実感できれば、部下への育成意欲も高まる
・組織全体として、管理職への昇進がキャリアアップの一環としてポジティブに捉えられる風土が醸成される
管理職候補研修を通じて前向きな意識を育むことは、個人のキャリア形成だけでなく、組織全体の活性化にもつながります。
(参考)管理職になりたくない社員の増加
パーソル総合研究所の「グローバル就業実態・成長意識調査(2022年)」によると、「管理職になりたい」と思っている人の割合はわずか19.8%でした。このような状況を変えるためにも、管理職候補研修で前向きな感情を育む仕掛けが重要です。
2-2.昇進後、管理職業務へスムーズに移行できる
管理職候補研修には昇進後の管理職業務へのスムーズな移行をサポートする効果があります。
管理職は、目の前の業務に加えて中長期の視点で事業や組織をマネジメントする役割が求められます。さらに、部下育成や他部署との調整、経営陣からの期待への対応など、対応すべき課題が多岐にわたります。
こうした管理職ならではの役割や課題に対して、必要なスキルや考え方を事前に身につけておくことで、昇進後もスムーズにスタートを切ることができます。
しかし、十分な準備がないまま管理職に就くと、これまで経験したことのない責任や課題に直面し、強いストレスや不安を感じるケースが少なくありません。
具体的には、以下のようなリスクが高まる可能性があります。
・目の前の課題に振り回され、戦略的な視点を持てなくなる
・必要以上に失敗を恐れ、新しい取り組みやチャレンジを避ける
・自己流のマネジメントに陥り、部下や周囲との信頼関係を築けない
・管理職という役割へのモチベーションが低下し、早期離職につながる
このような状況が続くと、チーム全体のパフォーマンス低下や、次世代管理職の育成難航といった、組織全体への悪影響も避けられません。
一方で、管理職候補研修を通じて、事前に役割理解やスキル習得を進めておくと、管理職本人だけでなく、組織全体にも以下のような効果が期待できます。
・管理職が自信を持って役割に向き合うことで、チーム全体の安定感やパフォーマンス向上につながる
・事業や組織に対する当事者意識が高まり、自発的な改善提案や前向きな行動が増える
・管理職への昇進が、キャリアのステップアップとしてポジティブに捉えられ、次世代リーダーの育成にも好影響を与える
・管理職同士の横のつながりも強化され、組織全体のコミュニケーションや連携力も向上する
このように、管理職候補研修を通じて心構えやスキルを整えることで、管理職への移行をスムーズにし、個人のキャリア形成と組織全体の成長を後押しすることができます。
2-3. 事業戦略を推進できる組織創りが進む
管理職候補研修には、事業戦略を推進するための組織づくりを加速させる効果があります。
どれほど優れた戦略があっても、それを実行できる組織と人材が揃っていなければ、戦略は実現しません。特に、管理職層が戦略の方向性を理解せず、日々の業務に追われるだけでは、戦略は机上の空論に終わってしまいます。
事業戦略を実現するためには、戦略を現場で実行できる管理職を育てることが不可欠です。
この準備が不十分なまま、管理職を登用してしまうと、以下のようなリスクが生じます。
・事業戦略を理解していないため、現場の短期的な課題解決に追われ戦略的な行動が取れない
・事業全体の方向性と、自部門の目標や施策が噛み合わず、成果が最大化されない
・理職自身が「なぜこの役割が必要なのか」を理解できていないため、役割に対する主体性や責任感が生まれにくい
・必要な人材やスキルが揃わないまま戦略を進めることで、事業そのものが停滞する
事業戦略と管理職の役割が分断されると、戦略と現場が噛み合わず、組織全体の一体感も失われる危険があります。
一方で、管理職候補研修を通じて、事業戦略に基づく管理職像や必要なスキルを事前に伝え、育成しておくと、組織全体に以下のような良い影響をもたらします。
・管理職候補者が事業戦略を「自分ごと」として捉え、主体的に関わる姿勢が醸成される
・事業戦略と組織運営がつながり、組織全体が同じ方向を向きやすくなる
・戦略推進に必要な役割を担う管理職層が整備されることで、組織全体の推進力が高まる
・「管理職=事業を担う重要なポジション」という意識が広まり、管理職へのポジティブな意識が醸成される
このように、管理職候補研修を単なるスキル研修にとどめず、事業戦略を推進するための人材・組織作りの場として活用することで、個人と組織の成長を両立させる効果的な取り組みにすることができます。
管理職候補研修には、「管理職になることへの前向きな意識醸成」「昇進後のスムーズな移行」「事業戦略を推進できる組織づくり」という3つの重要な効果があります。
個人の成長支援にとどまらず、組織全体の強化と事業戦略の実現にもつながる、非常に重要な取り組みです。
3. 【効果別】管理職候補者向け研修の内容例と注意点
2章で紹介した下記3つの効果得るための具体的な研修内容例と、実施での注意点をお伝えします。
・「管理職になることへの前向きな感情を育む」ための研修
・「昇進後、管理職業務へスムーズに移行できる」ようになるための研修
・「事業戦略を推進できる組織創りが進む」ようになるための研修
3-1. 「管理職になることへの前向きな感情を育む」ための研修
管理職候補研修では、「管理職になることへの前向きな感情」を育むことが重要です。
そのためには、研修の中で候補者自身が「管理職としての役割にポジティブな意味を見出せる」機会を作る必要があります。
ここでは、具体的な研修内容として以下の3つの方法を紹介します。
1)「ありたい姿」と「会社が求める管理職像」の統合
2)ハイパフォーマーな管理職のストーリーテリング
3)経営者との対話
1)「ありたい姿」と「会社が求める管理職像」の統合
管理職候補者自身の「ありたい姿(なりたい自分像)」と「会社が求める管理職像」をすり合わせるワークを行う方法です。
例えば、以下のようなテーマで対話やワークを行います。
・どのような組織が「素晴らしい組織」と言えるか
・自分が描く理想の未来はどんなものか
・その未来のために、自分はどんな働きかけができるか
こうした問いを考えることで、「管理職としての役割=自分自身が目指す未来の実現につながる」と実感できるようになり、管理職になることへの前向きな気持ちを育むことができます。
【実施のポイント】
1. 会社の期待を押し付けない
「会社が求める管理職像」ばかりを強調すると、管理職候補者は「会社のために無理やり合わせなければならない」と感じ、やらされ感につながります。
大切なのは、個人のありたい姿を尊重しつつ、会社の求める管理職像との接点を一緒に探すプロセスです。
2. 個人の「ありたい姿」を引き出す時間をしっかり確保する
候補者自身が「どんな管理職になりたいか」を考える時間を十分に取ることが重要です。
会社の期待を伝える前に、まず自分自身の価値観や理想を深掘りするワークを設けましょう。
3. 正解を提示しない
ありたい姿を探求する際には「こうあるべき」という正解を提示してしまうと、候補者が自分で考える余地がなくなり、納得感や主体性が育ちません。自分自身で考え、言語化し、自分なりの管理職像をつくるプロセスを大事にしましょう。
4. 対話を重視する
ワークやディスカッションを通じて、候補者同士で価値観を共有することで、多様なあり方を知ることができます。他者の考えを知ることで、「自分なりの管理職像」のイメージが広がる効果もあります。
5. 「ありたい姿」と「会社が求める姿」にギャップがあっても否定しない
候補者が思い描く理想像と、会社の求める姿にギャップがある場合もあります。
その際に、「どちらが正しいか」と判断するのではなく、「どうすれば双方が納得できる接点が見つかるか」を一緒に考える対話の場にすることが重要です。
候補者自身の「ありたい姿」と「会社が求める管理職像」を統合するプロセスは、一方的な押し付けではなく、双方向の対話によって行うことがポイントです。
「ありたい姿」と「会社が求める管理職像」の統合ワークを丁寧に行うことで、管理職という役割を自分ごととして捉え、前向きな気持ちや納得感を醸成することができます。
2)ハイパフォーマーな管理職のストーリーテリング
自社で活躍している管理職が、自身の経験や想いをストーリー形式で語る方法です。
「管理職としての仕事が、どのように自身の人生の豊かさにつながったか」を伝えてもらうことで、候補者に前向きな意識を育みます。
その際、成功体験だけでなく、リアルな苦労や乗り越えた過程を語ることが重要です。
華やかな話ばかりでは共感を得られず、「自分には無理だ」と感じさせる逆効果になる可能性があります。
(参考)ストーリーテリングとは
自身の経験や想いをオープンに、かつ、人間味を持ってストーリーとして伝える方法。抽象的な単語や情報を羅列するよりも、相手の記憶に残りやすく、得られる理解や共感が深い。組織の理念やビジョンなどを、メンバーに浸透、動機づける際に活用されることが多い。(ストーリーで話す方法と論理的・数値的に話を伝える方法とでは、人の記憶の残りやすさに最大22倍差が生じるとの研究結果もある。(スタンフォード大学 Jennifer Aaker教授))
【実施のポイント】
1. 成功談だけでなく、苦労や失敗も話す
「特別な人だからできた話」と受け取られないよう、リアルな困難とそれをどう乗り越えたかを伝えましょう。
失敗や壁にぶつかった経験、そこからどう乗り越えたのかをリアルに語ることで、候補者にとって身近で共感しやすい話になります。
2. 想いや葛藤を含めて話す
業務スキルや実績だけではなく、「なぜその役割に向き合おうと思ったのか」「管理職としてどんな葛藤や成長があったのか」といった人間らしい感情や価値観も伝えることが重要です。
ストーリーを通じて、管理職として働くことの意義ややりがいを候補者がイメージできるようにします。
3. 管理職候補者の不安や期待に寄り添う
「こんなことを知りたかった」という候補者の視点を意識して話を構成すると、候補者の納得感や共感が高まります。「自分もそう感じる」「その気持ち、分かる」という共感ポイントを意識すると効果的です。
4. 「自分には無理」と思わせない工夫
あまりに華やかな成功談や圧倒的な実績ばかりだと、候補者が「自分には無理だ」と感じてしまうことがあります。
最初は誰でも悩んだり失敗したりすることや、小さな成功体験の積み重ねが自信につながることなど、「等身大の姿」を伝えることで、候補者が自分事として受け止めやすくなります。
5. 一方的に話さず、対話を取り入れる
ストーリーテリングの後には、質疑応答やディスカッションを設け、候補者が感じたことを言葉にする機会を作ると、より学びが深まります。
ハイパフォーマーな管理職のストーリーテリングは、実際に活躍している管理職のリアルな経験や想いを伝えることで、管理職候補者に管理職という役割への前向きな感情を育みます。
3)経営者との対話
経営者と直接対話し、管理職への前向きな感情を育む機会を作る方法です。
「自分が組織の未来にどう関わっていけるか」を考えるきっかけを提供します。
対話では、以下のようなテーマについて話し合います。
・組織の未来像と管理職の役割について
・管理職候補者自身が描く未来像との共通点や相違点
・現在の組織課題を、経営者とともにどう乗り越えていくか
【実施のポイント】
1. 一方的なメッセージ発信にしない
経営者が想いやビジョンを一方的に語るだけでは、管理職候補者にとって「聞かされる場」になってしまい、心に響きません。
対話形式にし、候補者の考えや疑問、意見を引き出す場にすることが重要です。
2. 理想論だけでなく、リアルな課題も伝える
現場が抱えるリアルな課題や、経営の難しさなども率直に伝えることで、信頼感が高まります。「経営者も悩んでいる」「一緒に考えたい」というスタンスを示すことで、候補者も自分事として未来に向き合いやすくなります。
3. 経営者の影響力が強くなりすぎないよう工夫する
経営者の言葉は非常に影響力が強いため、候補者が意見を言いにくくなることがあります。「こうあるべき」という押し付けにならないよう、外部ファシリテーターを活用し、対話を促進する仕掛けを用意することが効果的です。
4. 「自組織の未来」と「候補者自身の未来」をつなげる
組織の未来だけでなく、「自分はその未来にどう関わるのか」「自分のありたい姿とどう重なるのか」を考える対話にすることで、未来のビジョンを自分事として捉えやすくなります。
5. 現場視点を否定しない
経営者目線と現場目線にはギャップがある場合も、互いの立場を理解し合う場にすることが重要です。現場のリアルな声を否定せず、互いの立場を理解し合うことを目的とした対話にすることで、信頼関係の構築につながります。
経営者との対話は、単なる「想いの共有の場」ではなく、管理職候補者自身が未来をどう担うかを考えるきっかけとして設計することがポイントです。
経営者と候補者が双方向に対話できる場をつくり、外部ファシリテーターの活用なども交えながら、納得感と主体性を引き出す対話を目指しましょう。
3-2.「昇進後、管理職業務へスムーズに移行できる」ようになるための研修
管理職候補研修では、昇進後の業務へスムーズに移行できるよう、管理職特有の課題や必要なスキルを事前に学ぶ機会を設けることが重要です。
ここでは、具体的な研修内容として以下の2つを紹介します。
1)自チームメンバーの理解
2)現管理職や管理職候補の強み・弱みへの対策
1)自チームメンバーの理解
管理職になると、「職務権限に基づく意思決定や決裁」など、チームを代表して判断を下す場面が増えます。この時、チームメンバーが管理職の判断に納得し、共に動いてくれる関係性が不可欠です。特に他部署との衝突や対立が発生した際にも、チームのまとまりが強ければ、乗り越えやすくなります。
そのため、チームメンバーとの信頼関係構築や、意思決定の背景を丁寧に伝えるスキルなどを、管理職候補研修の中で学ぶことが大切です。
【実施のポイント】
1. 「メンバー視点」から抜け出し、管理職としての視座を高める
一般社員時代は「自分の成果」に集中しがちですが、管理職には「チーム全体の成果を最大化する」役割が求められます。チーム視点・組織視点を持つ重要性を丁寧に伝え、視座を上げるマインドセットを促すことが大切です。
2. 信頼関係の構築を「スキル」として学ぶ
「信頼関係」は感覚的なものではなく、具体的な行動やコミュニケーションを通じて築くものです。
・意図や判断の背景を伝える力
・傾聴や対話スキル
・フィードバックの仕方
などを実践スキルとして研修内で習得できる設計にしましょう。
3. 「伝える」だけではなく「理解を得る」プロセスを意識させる
管理職としての方針や意思決定を、一方的に伝えるだけではメンバーの納得感は得られません。
・なぜその判断に至ったのか
・メンバーの意見をどう反映したのか
など、双方向コミュニケーションの重要性を強調することが大切です。
4. 現場で実践する機会を設ける
研修で学んだ「チーム理解や関係構築のスキル」を、実際のチーム運営で試せる機会を作ることが重要です。
研修だけで終わらせず、「実践→振り返り→学び直し」のサイクルを回す仕組みを取り入れましょう。
5. 管理職候補自身が理想のチーム像を言語化する
「どんなチームを作りたいか」「どのような関係性を築きたいか」を言語化し、主体的にチームを運営する意識を高めるワークを取り入れると効果的です。
管理職候補者が、「チームの成果を最大化する役割」を理解し、メンバーと信頼関係を築くための具体的なスキルとマインドを事前に身につけることで、昇進後のスムーズな業務移行につながります。
2)現管理職や管理職候補の強み・弱みへの対策
現管理職や管理職候補の強みと弱みを整理し、今後の事業戦略をふまえたうえで、強みをさらに伸ばす内容と、弱みをカバーする内容をバランスよく組み込む方法です。
強みをさらに強化することで、管理職昇進後に早期に成果を出しやすくなり、弱点を補強しておくことで、管理職になった際のつまずきポイントを減らせます。
強み・弱みの把握方法としては、上司や組織からの評価に加え、管理職候補者自身の自己評価やアンケートを活用する方法があります。
いずれの場合も、現場で活用できるスキルを研修内容として選定することが重要です。
【実施のポイント】
1. 強みだけ・弱みだけに偏らず、バランスよく設計する
強みを伸ばすことは重要ですが、それだけでは管理職に必要な総合力は身につきません。
反対に、弱み克服ばかりに焦点を当てると、候補者自身が自信を失い、モチベーションが下がる可能性があります。
「強みをさらに伸ばして武器にする」「弱みを最低限カバーする」の両面を意識した設計がポイントです。
2. 強み・弱みの把握は多面的に行う
上司や人事の評価だけではなく、候補者自身の自己認識や、周囲(同僚・部下など)からのフィードバックなど、複数の視点から強み・弱みを洗い出すことで、より実態に即した内容を設計できます。一方向の評価に偏らないよう注意が必要です。
3. 事業戦略との整合性を確認する
管理職候補個人の課題解決だけにフォーカスすると、組織が目指す管理職像とズレる可能性があります。
事業戦略の方向性や、管理職に求める役割を明確にした上で、強み・弱みの選定と優先順位づけを行いましょう。
4. 現場で使えるスキルを優先的に選ぶ
「知っているけれど、現場で活用できない」内容ではなく、実際の管理職業務で活かせるスキルを研修に盛り込みましょう。研修後に現場で実践し、振り返る機会を設けることで、学びが定着しやすくなります。
5. 研修選定のための事前アンケートの聞き方に注意
管理職候補へ研修選定のための事前アンケートを行う際は、「プレイヤーとして必要なスキル」ではなく、「管理職になるために必要なスキル」に焦点を当てて聞く必要があります。
前提を伝えずにアンケートを実施すると、プレイヤーとしての業務スキル強化希望が出てきてしまう可能性があるので注意しましょう。
チームや管理職候補の強みをさらに伸ばし、弱みを事前に補うことで、昇進後のスムーズなスタートや早期の成果につながります。
3-3. 「事業戦略を推進できる組織創りが進む」ようになるための研修
事業戦略を推進するための組織づくりを促進するには、自社の事業戦略に合った研修内容を設計することが重要です。
どのようなスキルや知識が事業戦略上必要なのかを整理し、それに基づいて管理職候補研修を実施していく必要があります。
例えば、「新規事業や新サービスを立ち上げたばかりで、その領域を担う管理職を育成したい」という状況であれば、
・物事を前に進めるリーダーシップの開発
・新規事業開発を推進するためのプロジェクトマネジメント
といったスキルを重点的に学ぶ研修が効果的です。
【実施のポイント】
1.事業戦略と直結したスキルを選定する
事業戦略を実現するために、管理職に求められるスキルや知識を洗い出し、戦略とスキルの紐づけを明確にした上で研修内容を設計することが重要です。
2.汎用的な研修で済ませない
一般的な管理職研修をそのまま実施しても、自社の事業戦略や組織課題に合っていなければ、実務に活かされにくいため、自社オリジナルの内容にカスタマイズする視点が欠かせません。
3.研修後にスキルを発揮できる場を用意する
研修で学んだスキルを実際の業務で試せる機会がなければ、定着や成果にはつながりません。研修内容にリンクしたポストやプロジェクトへのアサイン計画も合わせて検討する必要があります。
4.研修設計時に経営層・事業責任者も巻き込む
事業戦略を推進する組織づくりには、経営層や事業責任者が求める役割や期待を反映させることが不可欠です。人事部門だけで完結せず、事業サイドと連携して内容を設計しましょう。
5.中長期の視点でスキル強化を計画する
事業戦略に求められるスキルは、短期的に身につくものばかりではありません。管理職候補段階から継続的にスキル強化を図るために、研修とOJTを組み合わせた中長期の育成計画を立てることが重要です。
事業戦略を確実に推進するためには、事業戦略と連動した管理職候補研修の設計が欠かせません。
学んだスキルを現場で活かせる機会を設けたり、経営層や事業責任者も巻き込みながら、中長期的な視点で人材育成を進めることが、事業を支える強い組織づくりにつながります。
【関連記事】管理職研修の必要性を見極める方法と、経営者・管理職への理解の促し方
管理職候補者向け研修は、単なるスキル習得にとどまらず、管理職になることへの前向きな感情醸成、昇進後のスムーズな業務移行、事業戦略を推進できる組織づくりといった、組織全体の成長にもつながる重要な役割を担っています。
個人の成長と組織の戦略的な成長を同時に実現する研修を設計し、事業を支える強い組織づくりを目指しましょう。
4. まとめ・管理職候補研修はアーティエンスにお任せください
管理職候補者向け研修は、単なるスキル研修ではありません。「管理職への前向きな感情醸成」「昇進後のスムーズな移行」「事業戦略を推進できる組織づくり」という3つの重要な効果を生み出す、組織全体の成長基盤を支える重要な施策です。
管理職へのネガティブなイメージを払拭し、管理職候補自身の「ありたい姿」と会社が求める管理職像をすり合わせながら、主体的に役割を担っていける管理職を育てることが、組織の成果最大化や事業戦略の実現につながります。
アーティエンスでは、管理職候補者自身のありたい姿と会社が求める管理職像を丁寧にすり合わせながら、個人と組織の未来をつなぐ管理職候補研修を設計・提供しています。
単なるスキルインプットにとどまらず、管理職候補者が主体的に役割に向き合い、実際の業務で力を発揮できるよう、実践的なプログラムをご用意しています。
貴社の事業戦略に合わせたオーダーメイド設計も可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
管理職候補研修を通じて、管理職候補者自身が未来への手応えを感じながら、管理職に前向きに挑戦していく姿を生み出しましょう。
そうした管理職が増えることで、個人と組織がともに成長し続ける未来を期待できます。
管理職候補者研修をご検討中の人事責任者様・担当者様へ
こんな悩みをおもちではありませんか?
- 候補者研修企画の具体的なプロセスが知りたい
- 予算内でできる最適な研修を知りたい
- 自組織の課題を解決できる研修を知りたい
- 成功事例や研修効果を高めるノウハウを知りたい
研修の効果を最大化するためのヒントが、たった1回の相談で得られます。社内研修・人材育成でお悩みの方はお気軽にご相談ください。