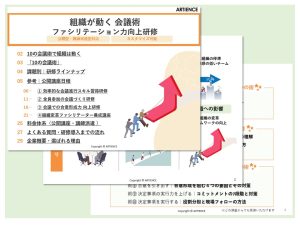- [ コラム ]
【管理職が潰れない組織へ】管理職のメンタルヘルス対策
- 「管理職が潰れないためにも、対応をしないと…」と考えている人事・経営者の方や、「もう無理だ。限界、このままだと潰れる…」と感じている管理職の方が、本コラムにたどり着いたのではないでしょうか。本コラムでは、管理職を潰さないようにするためには、
- 詳細を見る
【事例あり】管理職の役割に起きた変化と、自組織が強化すべきポイントを見つけよう
更新日: ー
作成日:2022.9.12

「管理職が担っている役割が多く、パフォーマンスが下がっている…」
多くの組織で旧来の管理職の役割から新たな役割が追加され、疲弊している状態が起きています。
管理職の役割が増え、かつ、不明確になり、組織側も何を優先して育成すべきか見つけられず、適切な育成を行えない状態になっているのではないでしょうか。
このままでは、管理職の成長を期待することは難しく、組織の成長も停滞してしまいます。
そこで本コラムでは、旧来の管理職の9つの役割に起きた変化を明記しています。そして、自組織で強化すべきポイントを整理する方法を、事例を用いてお伝えします。
自組織なりの管理職の役割を整理し、適切な対策を行い管理職の成長に繋げていきましょう。
1)管理職の9つの役割と大きな変化
管理職の9つの役割に、大きな変化が起きています。
1.チーム・部署における業務遂行
2.職務権限に基づく意思決定・決裁
3.情報の伝達と共有
4.メンバーの育成・評価
5.チームビルディング・モチベーション管理
6.労務管理・健康管理
7.コンプライアンス管理
8.プレイヤー業務との両立
9.リーダーシップの発揮
それぞれの役割にどのような変化が起きたのか、下記の項目で具体的にお伝えしていきます。
1. チーム・部署における業務遂行
管理職の役割である「チーム・部署における業務遂行」は、昨今のコロナ禍、そしてVUCAといわれる変化が激しく未来予測が不可能な状況を加味してアジャイルが求められています。
| コロナ前 | 自身が所属する部(チーム)が担う業務の遂行状況全般を管理・運営します。 業務は「計画」─「遂行」─「振り返り(改善)」という一連のサイクルをたどり、行っていきます。 多くの組織においては、管理職は事業部の年間計画を行い、都度振り返り(改善)を行いながら、業務品質を維持・向上していきます。 そのほか、新規事業、新企画サービスの立案・進行の責任者として業務を担うケースもあります。 |
| 現在 | 緻密な計画よりも柔軟・実験的な業務遂行へ 緻密な計画よりも、アジャイル(素早く実行、早く失敗し(軌道修正を取り)、早く学習し、早く成長していく)という考えのもと、スピード感を持ちながら柔軟に業務遂行していくことが、これからの管理職には必要とされていくでしょう。 |
2. 職務権限に基づく意思決定・決裁
管理職の役割である「職務権限に基づく意思決定・決裁」は、急激な変化にも対応できる意思決定スピードが求められています。
| コロナ前 | マネジャーは職務権限を持ち、それら権限に基づく意思決定や決裁を求められます。 権限の範囲は組織や部(チーム)によって異なりますが、例えば以下のようなものがあります。 ・部(チーム)の事業計画および予算の決定 |
| 現在 | 急激な変化に対応できる意思決定スピードを 管理職は、日々の業務で多くの意思決定を求められます。 変化の激しい現代では、従来のフローでは決定が現場に降りてくる頃にはもうすでに状況が変わっていて、変化に対応できなくなっているでしょう。 |
3. 情報の伝達と共有
管理職の役割である「情報の伝達と共有」では、コロナ禍以降、戦略的なコミュニケーション機会の創出と、スピード感ある情報共有と仕組化が求められています。
| コロナ前 | 部(チーム)が円滑に業務遂行を行えるために必要な情報を入手、伝達、共有していくことも管理職の役割のひとつです。 管理職が担う情報としては、例として以下のようなものがあります。・経営トップのメッセージ(ビジョン・ミッション等)を理解・咀嚼し、現場に浸透 ・社内外の情報収集および周辺状況の分析 |
| 現在 | 戦略的なコミュニケーション機会と環境創りを 対面コミュニケーションが激減した今、より戦略的にコミュニケーションの機会を創出し、情報共有のスピード、質や量を高めていく仕組み創りが、管理職には期待されています。 以下に取り組むだけでも、チームの情報共有への意識が変わってくるかもしれません。 ・自部署の情報をできる限りオープンにし、メンバーの情報量をそろえる |
4. メンバーの育成・評価
管理職の役割である「メンバーの育成・評価」は、対話を通じて共に学び続け、共に成長していく役割が求められています。
| コロナ前 | 部(チーム)内のメンバーの育成や評価も、管理職の重要な役割です。 部下一人ひとりに当人たちの特性や性格、長所・短所を踏まえた、指導・育成・評価を行っていき、ときに役割や配置の調整を行いながら、部(チーム)全体の業務品質を向上・安定させていくことが求められます。 |
| 現在 | 対話を通じて共に学び続け、共に成長していく 過去の成功体験やノウハウ共有だけでは変化に対応できなくなった今、管理職自身も、メンバーと共に学び続け、成長していく必要があります。 評価にしても、対話によるフィードバック(会話の中などでも)を多く行い、部下の意識行動の強化・軌道修正を行います。そのことによりwitnコロナにあわせた目標管理も可能になるでしょう。 |
5.チームビルディング・モチベーション管理
管理職の役割である「チームビルディング・モチベーション管理」では、管理職自身がコントロールするという文脈から、セルフマネジメントの促進が求められるようになっています。
| コロナ前 | 部(チーム)が円滑に機能していくうえでのチームビルディング、モチベーション管理も管理職の重要な役割です。 1) 共通の目的・目標があること の3つが必要不可欠と言えます。 それら三点を活性化する働きかけも、管理職に求められます。 |
| 現在 | 心理的安全性を高め、メンバーのセルフマネジメントの促進 テレワーク環境では、より意識的にチームビルディングを行う必要があります。 メンバーの目標への意識を高め、達成のために自然発生的に情報共有や助け合いが行われる心理的安全性の高いチームを、管理職起点で創ることが重要です。 |
6.労務管理・健康管理
管理職の役割である「労務管理・健康管理」では、従来の内容は変わらないものの可視化することや信じる管理が求められています。
| コロナ前 | 部(チーム)内のメンバーが業務に集中できる環境を目指すうえでの、労務管理・健康管理も管理職が担います。 主な業務内容としては、以下が挙げられます。 ・メンバーの労働時間や勤務時間の管理 |
| 現在 | テレワーク時代の信じる労務管理 働き方が多様となった現在、仕事に取り組む姿を直接見る機会が減ています。 しかしながら、必要以上に進捗状況を監視・指示され、逐一の報告を求められる仕事から、楽しさや喜びを感じることは難しいでしょう。 |
7.コンプライアンス管理
管理職の役割である「コンプライアンス管理」では、SNS等での情報漏洩などのリスクが高まっています。リスクの周知をこれまで以上に実施することが求められています。
| コロナ前 | 部(チーム)のコンプライアンス(法令やルールを順守すること)管理もまた、管理職の重要な役割のひとつです。 ・個人情報の適切な管理 |
| 現在 | 新入社員・若手社員のコンプライアンス意識の強化がさらに重要に |
8. プレイヤー業務との両立
管理職の役割である「プレイヤー業務との両立」の必要性は、増しています。プレイングマネージャーとして活躍するためには、メンバーを主体的・自律的に行動できる人材にし、管理職自身の管理業務の時間を減らすことが大切です。
| コロナ前 | 管理業務と現場業務(プレイヤー業務)を並行して行う「プレイングマネジャー」が、企業規模を問わず、現在の日本においては管理職のスタイルとして主流になってきています。 プレイングマネジャーという概念が日本のビジネスの世界に登場したのは、バブル崩壊後です。経営状況悪化による人件費削減、管理職ポストの激減により、実務とマネジメントを兼任できるような人材が求められ始めました。 |
| 現在 | メンバーの自己組織化の促進で、プレイヤー業務との両立を図る 業務の複雑性や難易度が増す現在、管理職自身が率先してプレイヤー業務を担う場面も多くなっています。 管理職のプレイヤー要素の増加に比例して、マネジメント業務やメンバーとのコミュニケーションに充てる時間は少なくなっています。 管理職からの指示や命令によって受け身で動くのではなく、メンバー一人ひとりが主体的・自律的に行動していくこと。そして、その相互作用によりチーム力を高め、生産性を上げていくことが必要不可欠です。 |
9.管理職としてのリーダーシップ発揮
管理職の役割である「管理職としてのリーダーシップの発揮」は、管理職自身のリーダーシップの発揮から、メンバーがリーダーシップを発揮できる機会を創る存在に変化しています。
| コロナ前 | 管理職は、マネジメント業務だけではなく、リーダーとしての働きかけも必要です。 マネジメントの概念=「決められたことを正しい方法でやること」 と言われます。状況に応じて 二つを使い分けながら、業務を進めていく必要があります。 |
| 現在 | メンバーのリーダーシップ発揮を解放する 明日の正解が分からない時代となり、強いリーダーだけでは、立ち行かなくなると言われています。全員が当事者意識を持って、主体的に対応しなければ、変化のスピードについていけないと考えられるからです。 だからこそ、管理職は、メンバーがリーダーシップ(周りへの影響力)を発揮できる機会を創っていく必要があります。 |
2)【事例あり】自社が強化すべき管理職の役割を見つける方法
前章の内容を基に、自組織の管理職に強化すべき点を見つけていきましょう。
具体的には、下記の手順で進めます。
1.管理職の強みと、弱みと捉える
2. 目指す状態から、管理職が注力するポイントを明確にする
3.変革を促す施策を実行する
それぞれの詳細を、事例と共にお伝えします。
1. 管理職の強みと、弱みを捉える
まずは、自組織の管理職の強みと弱みを整理しましょう。サーベイの結果や経営層の意見も反映できると、より納得度の高い内容を創ることができます。
例えば当社が管理職育成をご支援しているお客様では、経営陣と一部の管理職が入った対話の中で、下記の状況が見られました。
【メンバーの育成・評価】
⇒対話を通して、メンバーと学びあう風土がある
【チームビルディング・モチベーション管理】
⇒エンゲージメント調査でも、管理職とメンバーの関係性は良いと出ている
【コンプライアンス管理】
⇒コンプライアンスに対して、厳しいルールがあるため、問題は起きにくい
【職務権限に基づく意思決定・決裁】
⇒経営陣の顔色伺い、忖度した意思決定をする
【情報の理解と伝達・共有】
⇒部分最適になることが多かったり、メンバーに情報が落ちていないことがある
【リーダーシップの発揮】
⇒管理職中心のチーム創りになっていて、管理職への依存度が高い
2. 目指す状態から、管理職が注力するポイントを明確にする
管理職の役割の中で、強み・弱みが明確になったら、組織をどのように変えていきたいか、そして注力点を考えます。
「1. 管理職の強みと、弱みを捉える」のお客様は、「管理職が部分最適ではなく全体最適を持ってほしい。未来の経営者になっていくためにも、腹をくくって意思決定をしてほしい」という経営者の想いをもとに、注力ポイントを考えました。
以下の強みから、管理職同士・チーム内の関係性はよい状態であり、管理職同士・チーム内でしっかり議論・対話ができる状態にあることは分かりました。
【メンバーの育成・評価】
⇒対話を通して、メンバーと学びあう風土がある
【チームビルディング・モチベーション管理】
⇒エンゲージメント調査でも、管理職とメンバーの関係性は良いと出ている
強みを活かし、管理職同士・チーム内で議論をして、意思決定をしたり、経営陣に相談できる状態をめざすこととなりました。
議論・対話をするには、情報の理解と伝達・共有が必要です。そこで、弱みでもある、下記二つの役割を強化していくことになりました。
【職務権限に基づく意思決定・決裁】
【情報の理解と伝達・共有】
※ 今回は、管理職が中心になって、物事を進めてほしいとの意向もあり、3点目のリーダーシップの発揮への対策は、ステイとなりました。
3.変革を促す施策を実行する
【職務権限に基づく意思決定・決裁】【情報の理解と伝達・共有】の2つの役割を強化するために、管理職会議を通して、管理職育成を行いました。
研修のような一過性の形ではなく、普段の仕事を通して、役割強化を図りました。 管理職の会議は以下のように設計しました。
目標 : 会議によって異なる
管理職会議のルールも考えました。
・可能な限り自部署・他部署を問わず普段から情報をオープンする
・管理職会議までに、自身の考えを持ってくる
・会議の中で、意思決定する(必要に応じて、経営者の判断を仰ぐ)
・ファシリテーターを持ち回りで行い、全体最適を常に促す
始めは、会議を進めるのは難しいため、当社のファシリテーターが会議に入り、ファシリテーションし、徐々に管理職で回せるようにしました。
※ 本お客様の管理職の方々は、当社の社内ファシリテーター育成コースも受講されました。
このように、管理職の役割と強み・弱みを明確にした上で「目指す状態」と「注力点」を考えることで、対策検討が進みやすくなります。
3)自社が強化していく管理職の役割を見極める際の3つの注意点
管理職の役割を定義する際に、3つの注意点があります。
その注意点を理解すると、管理職の役割定義をより効果的に実施することが可能です。それぞれ説明します。
1. 管理職の影響力を高めるために、スキルとあり方の両方にフォーカスする
管理職は、組織への影響力が高いため、マネジメントスキルを学ぶ必要もありますし、また人としても成熟度を高めていく必要があります。
どんなにスキルがあっても、人として尊敬できなければ、部下はついていきませんし、経営者や他部署の管理職も信用・信頼できません。
逆にどんなに人格者であっても、マネージャーとしてのスキルを持っていなければ、頼り無くなってしまい、マネージャーとして機能しません。
両方を高めることが必要です。
2. 仕組化により、成果と成長を両立させる
管理職は、短期的成果と、中長期的成長という対立関係を乗り越えることを求められます。この対立関係を解決するには、仕組化が必要になってきます。
仕組み化は、一般的に「いつ、どこで、誰がやっても成果(アウトプット)が出る状態」と定義にされることが多いですが、ここでいう仕組化は成果だけではなく「成果を出しながら成長することができるをフローを作ること」です。
この時、注意が必要なのは、一回作って終わりではなく、アップデートし続ける仕組化です。時代は変わり続けるので、常に時代や状況に適応していくことが重要です。
例えば、withコロナになり、今までの営業方法が通用しない場面においては、新しい営業方法を作り、仕組化する必要があります。
その際は、「短期的な売上をどう上げていくか」という観点と、「チームとしてナレッジや経験がたまり、メンバーの成長を促すにはどうしたらいいか」を考えていく必要があるでしょう。
「成果なのか?成長なのか?」ではなく、成果と成長を統合するために仕組みを考えて、アップデートし続けることを、役割定義に入れ、促していくことが必要です。
3. 管理職のパフォーマンスを最大化するために、管理職の業務量を調整する
管理職は、業務量も多く、また役割も多いです。そのため、管理職の業務量の調整を、管理職の上司である事業責任者(時には経営者)と、また管理職本人が行うことが必要です。
管理職に新しい役割をアサインする場合は、慎重に行いましょう。管理職自身の負担という問題だけではなく、管理職の仕事の質が低下する場合もあります。
昨今の変化の早い時代では、管理職の役割自体が変わっているとも言えるかもしれません。管理職が一人で仕事を抱え込むのではなく、今まで以上にチームで行うことを意識する必要があります。部下との共創・協働をどのように行っていくかを考えていく必要があります。
例えば、管理職に新しいプロジェクトマネージャーを任せるのであれば、今アサインしている業務を他の管理職に分散するか、一部上長が引き取るなども時には必要でしょう。もしくは、「今までやっていたから」という仕事を見直して、無くしていくことも必要かもしれません。
また管理職自身も、次の管理職育成を兼ねて、自身の仕事の一部を部下に任せていくことも必要です。もちろん任せる場合は、フォローは前提です。一人の部下に任せる場合もあれば、複数の部下に任せてもいいかもしれません。
管理職が役割を全うするためにも、今組織にとって、管理職に何を求めるかを考えて、業務量を調整していく必要があります。
4) まとめ
時代にあった管理職の役割を理解し、自組織にあった管理職の役割を定義することで、組織変革が進みます。
具体的には、人事制度の見直しや、今必要な管理職の採用、管理職の育成などから、管理職のパフォーマンスは上げることができるでしょう。自組織に必要な役割が定義でき、育成ができれば、経営者は現在の事業に不安を抱えることなく、新規事業開発やM&A、上場準備など他の施策に対して集中できるでしょう。
そして管理職自身も、自身の役割を認識することで、迷いも少なくなります。また、成長にもつながります。経営陣からの信用・信頼だけではなく、部下や他部署からの尊敬の念も持たれるでしょう。
自組織にあった管理職の役割をまずは定義して、今何をするべきか考えてみてください。
外部の力も必要な場合もあると思いますが、その時は新しい管理職の役割を理解している外部パートナーを選ぶのがオススメです。
管理職の役割を定義しながら、変革を進めたいということでしたら、ぜひ当社にお問い合わせいただければと思います。