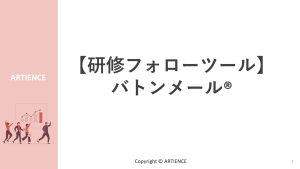-
[ コラム ]
管理職研修の必要性を見極める軸と、実施を妨げる要因への対策を紹介
- 「管理職研修を実施する必要があるのか、判断ができない…」「管理職研修を提案しても“今じゃない”、“必要ない”と言われてしまう…」管理職研修について、このようなお悩みをお持ちかもしれません。管理職研修は、組織の中核を担う管理職のスキルや意識を
- 詳細を見る
意味がない管理職研修からの脱却!12の失敗パターンと解決策
更新日:
「管理職研修を実施しても、現場での行動変容につながらない」
「管理職研修の満足度は高いのに、成果が見えにくい」
「せっかくの管理職研修が、ただの一過性のイベントになってしまう」
こんなお悩みをお持ちではありませんか?
多くの企業が管理職研修を実施しているものの「効果を実感できない」「実際の業務に活かされていない」という課題を抱えています。
では、どうすれば「意味のある管理職研修」にできるのでしょうか?
本コラムでは、意味がない無駄な管理職研修の特徴を12パターンに分けて解説し、それを回避するための具体的な対策についてご紹介します。また、効果的な管理職研修のプロセスもお伝えします。
意味がない管理職研修を排除し、研修の効果を最大限受け取って、管理職の変容を促しましょう。管理職が変わると、自ずと組織も変わってきます。

大学卒業後、大手通信会社、アルー(株)勤務後、2010年にアーティエンス(株)を設立。業界歴17年。大手企業から、中小企業、ベンチャー企業の人材開発・組織開発の支援を行っている。専門分野は、組織開発、ファシリテーション。
目次
- 1)意味がない無駄な管理職研修とは「変化をもたらさない研修」
- 2)意味がない無駄な管理職研修の12パターンと対策
- 2-1. 経営者の考えが一方通行で伝えられている
- 2-2. 研修のプログラムや講師のアプローチが厳格すぎる
- 2-3. 過去の研修内容をそのまま継承している
- 2-4. 一時的な流行やトレンドに頼りがち
- 2-5. 古い文脈に縛られ、時代に合った内容になっていない
- 2-6. オンライン動画や講演など、インプットに偏っている
- 2-7. 学びを詰め込み過ぎており、重視すべき点が不明瞭
- 2-8. 効果を確認できていない、もしくは、適切な方法でない
- 2-9. 講師が一方的にあるべき論を提示し、説得している
- 2-10. 受講者の実情にそぐわない
- 2-11. 単発の研修で終わり、フォローアップが不足している
- 2-12. 適正な予算が配分されていない
- 3)意味がない管理職研修にしないための5つのプロセス
- 4)まとめ・効果的な管理職研修はアーティエンスにおまかせ
1)意味がない無駄な管理職研修とは「変化をもたらさない研修」
意味のない研修とは「管理職に変化をもたらさない研修」のことです。
研修を受けたにもかかわらず、管理職が何も変わらなければ、それは意味のない研修になってしまいます。
逆に、意味のある研修とは、管理職が「認知」と「行動」の両面で変化する研修です。
●認知の変化とは、物事の捉え方や考え方の変化のことです。
例)「部下を管理する立場」から「部下の成長を支援する立場」へと意識が変わること、など
●行動の変化とは、実際の言動の変化のことです。
例)これまで指示命令型だったマネジメントを、対話を重視した関わり方に変えること、など
意味のある管理職研修にするためには、管理職が「認知」と「行動」の変化を起こせるかどうかを意識することが重要です。
2)意味がない無駄な管理職研修の12パターンと対策
意味のない無駄な管理職研修になってしまう原因として、以下の12パターンのいずれかに当てはまっている可能性があります。
これらについて具体的に紹介し、対策を説明します。
2-1. 経営者の考えが一方通行で伝えられている
管理職研修の中で、経営者の考えが一方通行で伝えられているだけでは、意味のないものになりがちです。
その理由は、大きく2つあります。
・時代背景の変化
現代は価値観の多様化が進み、それを尊重する風潮が強くなっています。そのため、一つの価値観を押し付けても、管理職は拒否感や違和感を抱くことが多いのです。
・当事者意識と主体性を抑えてしまう
管理職が主体的に考える機会を奪われると、認知変容(考え方の変化)や行動変容(実際の行動の変化)は起こりません。単なる受け身の研修になり、研修後も何も変わらない可能性が高いのです。
よくある失敗パターン
経営者が自分の言いたいことをただ伝えても、管理職はその場では話を聞いている態度を取りますが、実際は何も変わりません。話は聞くものの、自身とは無関係の話として捉える管理職も多いでしょう。
研修講師に言わせたとしても、結果同じです。管理職は何も変わらないか、もしくはエンゲージメントの低下が起きてしまうこともあります。
対策:経営者と管理職が双方向のコミュニケーションを取れるようにする
管理職研修内で、経営者の考えを紐解く対話の時間を設けるといいでしょう。対話を設けることで、管理職自身が内省し、自身の仕事と結び付けていくことができます。
可能な限り経営者と管理職が対話できるような環境をつくり、双方向のコミュニケーションを取れるようにすると理解をしあえて、変わるきっかけを作りやすいです。
2-2. 研修のプログラムや講師のアプローチが厳格すぎる
管理職研修のプログラムや講師のアプローチが厳格すぎると、意味のないものになってしまうことがあります。
その理由は、大きく3つあります。
・受講者の反発が起き、研修が進まない
厳しすぎる研修では、管理職が強いストレスを感じ、研修の内容を受け入れにくくなります。結果として、本来の学びよりも反発心が生まれ、研修が機能しなくなることがあります。
・自己効力感が低下し、学びが定着しない
過度に厳しい指導を受けると、受講者は「自分にはできない」と感じやすくなります。自己効力感が低下すると、研修で学んだことを現場で実践しようとする意欲が湧かなくなる可能性が高まります。
・研修後、学びが定着せず元の状態に戻る
研修中に強いプレッシャーをかけることで、一時的に意識が変わることはあります。しかし、それは特殊な環境下で生まれる変化であり、職場に戻るとすぐに元の行動パターンに戻ってしまうケースが多いです。
よくある失敗パターン
合宿形式の厳しい管理職研修では、受講者が一時的に奮起することがあります。
しかし、研修後に現場へ戻ると元の環境に引き戻され、研修の効果が持続しないことがほとんどです。
場合によっては、研修による強制的な変化に対する反動で、管理職のモチベーションが低下し、組織へのエンゲージメントが下がることもあります。
対策:厳格すぎないアプローチで、実践的な学びを重視する
研修を意味のあるものにするためには、厳しさだけで変化を促そうとするのではなく、実践的な学びを重視することが重要です。
具体的には以下の点を意識しましょう。
・適度な負荷をかけつつ、管理職が主体的に考える時間をつくる
・現場で活かせる具体的なスキルやアクションプランを研修内で作成する
・受講者同士の対話を取り入れ、現場のリアルな課題を解決するワークを実施する
管理職に対してどのような変化を望み、その変化を生むためにはどうしたらいいかを企画段階から再度考えることが重要です。
2-3. 過去の研修内容をそのまま継承している
管理職研修の内容を毎年同じものにしていると、現場の変化に対応できず、意味のない研修になってしまうことがあります。
その理由は、大きく2つあります。
・組織の方針や環境が変化している
企業の戦略や組織の方針は年々変わります。それにもかかわらず、過去の研修内容をそのまま踏襲していると、現在の課題に合わなくなる可能性があります。
・受講者がすでに知っている内容では、学びが生まれない
長年同じ研修を繰り返していると、受講者にとって新しい学びがなく、研修へのモチベーションが低下することがあります。
よくある失敗パターン
新任管理職研修を5年以上同じ内容で実施しているケースでは、組織の戦略や求められる管理職の役割が変わっているにもかかわらず、研修の内容がそれに対応できていないことがあります。結果として、受講者は「今の自分には関係のない話だ」と感じ、研修を無駄に思うことがあります。
対策:毎年、研修の内容を見直し、現場の課題に合わせる
基本的に毎年アップデートするものだという前提で、現場の管理職が直面している課題をヒアリングし、研修内容を確認しましょう。
ただ、その工数を割くのが難しい場合は、信頼できる研修会社に相談し、今の自組織にあった研修内容を相談しながら決めていくと良いでしょう。
2-4. 一時的な流行やトレンドに頼りがち
流行のトピックを取り入れた研修は、一見すると時代に合ったものに思えます。しかし、組織の課題に合わない研修では、効果が得られないことがあります。
その理由は、大きく2つあります。
・トレンドの内容が自社に適しているとは限らない
「DXが重要だからDXの研修をやろう」など、流行に乗るだけの研修では、自社にとって本当に必要な学びになっているかが不明確です。
・他社の成功事例が、自社でも成功するとは限らない
「他社で成果が出た管理職研修をそのまま導入する」ケースでは、企業文化や現場の状況が異なるため、効果が得られないことが多いです。
よくある失敗パターン
経営者の知人が「この研修が良かった」と紹介したものをそのまま導入するケースでは、実際に自社の管理職に必要な学びなのかを検討せずに研修を実施し、効果が得られないことがあります。
対策:流行ではなく、自社の課題に基づいた研修を選ぶ
管理職研修の企画の際に、世の中で流行っている内容やトレンドが、本当に自組織にマッチしているかを考えることが必要です。
「なぜこの研修が必要なのか?」を明確にし、自社の課題をもとに研修を設計するようにしましょう。
2-5. 古い文脈に縛られ、時代に合った内容になっていない
管理職研修の内容が過去の考え方や手法に基づいていると、時代の変化に対応できない研修になってしまうことがあります。
その理由は、大きく2つあります。
・環境の変化に対応できない
コロナ禍やテクノロジーの進化により、働き方やマネジメントのあり方は大きく変わりました。しかし、過去の成功体験に固執し、今の時代に合わない内容の研修を続けていると、管理職は現場で活用しにくくなります。
・実際の仕事の進め方とズレが生じる
ビジネス環境の変化が激しい現代において、従来のマネジメント手法が必ずしも最適とは限りません。研修で伝えられる内容が今の仕事の進め方や意思決定のスピード感に合っていない場合、管理職は学びを活かせず、かえって混乱を招くこともあります。
よくある失敗パターン
研修の中で、「管理職は現場をしっかり管理することが重要」と伝えていても、現在の組織では「管理」よりも「支援型リーダーシップ」が求められているというケースがあります。
受講者が「この内容は今の時代に合っていない」と感じると、学びが実践につながらなくなります。
対策:最新のマネジメント手法を取り入れ、現場の実情に合わせる
管理職研修を時代に適したものにするためには、今の働き方や組織の変化を反映した内容にアップデートすることが大切です。
まず、企業の戦略や組織文化に合わせて「今の時代に求められる管理職の役割」を明確にし、その役割を果たすために必要な知識やスキルを研修内容に組み込みましょう。
その際の参考として研修会社が開催しているセミナーなどに参加し、現代に求められている管理職像や、管理職が気をつけるべきことなどの情報を収集し、研修企画に活かすことをおすすめします。
2-6. オンライン動画や講演など、インプットに偏っている
管理職研修をオンライン動画や講演などのインプット中心で実施すると、実践につながらず、意味のないものになってしまうことがあります。
その理由は、大きく2つあります。
・見ただけ・聞いただけでは、行動変容が起きない
動画や講演で情報を得ることは大切ですが、それだけでは「自分ごと」として捉えにくく、現場での行動変容につながりにくいです。
・強制的な視聴では、学びが定着しにくい
「とりあえず動画を見せる」「講演を聞かせる」といった形式では、受講者が受け身になりがちです。強制的に視聴させても、自分の業務にどのように活かすかを考えなければ、実践にはつながりません。
よくある失敗パターン
オンライン研修の導入で「とりあえず学び放題の動画サービスを契約」したが、結局、管理職が動画を視聴して終わりになり、行動変容につながらなかったというケースがあります。
対策:アウトプットの機会を設ける
オンライン研修や動画研修を効果的にするためには、インプットだけで終わらせず、その後のアウトプットを意識することが重要です。
例えば、動画や講演を「前提知識を得る場」と位置付け、その後にディスカッションや実践の場を用意することで、学びが定着しやすくなります。
また、研修の前後にフォローアップセッションを実施し、学んだ内容が現場でどのように活用されているかを確認することも効果的です。
2-7. 学びを詰め込み過ぎており、重視すべき点が不明瞭
研修内容を多く詰め込みすぎると、何を重視すればいいのかが分からなくなり、研修の効果が薄れてしまうことがあります。
その理由は、大きく2つあります。
・研修の焦点がぼやける
あれもこれもと盛り込みすぎると、受講者は「結局何が一番重要なのか?」が分からなくなってしまいます。
・実践しにくくなる
多くのことを一度に学んでも、現場で実践するのが難しくなり、結果的に何も定着しないことがあります。
よくある失敗パターン
「1on1スキル」「評価制度」「チームビルディング」「ダイバーシティ」など、多くのテーマを1回の研修で扱ってしまい、どれも浅い学びに終わってしまうというケースがあります。
対策:学びのポイントを絞り、段階的に学ぶ
研修を効果的にするためには、テーマを厳選し、「この研修で一番伝えたいこと」を明確にすることが大切です。
また、半年〜1年間のプログラムとして管理職が段階的に学べる仕組みをつくることで、無理なくスキルを身につけることができます。
2-8. 効果を確認できていない、もしくは、適切な方法でない
管理職研修の効果測定を行わない、または誤った方法で測定すると、研修の成果が見えず、意味のない研修になってしまうことがあります。
その理由は、大きく2つあります。
・研修の成果が分からない
研修を実施しても、その後の変化を確認しなければ、管理職が本当に成長したのか、組織にプラスの影響があったのかを判断することができません。効果が不明確なままでは、次回の研修改善にもつながらず、継続しても成果が得られない研修になる可能性があります。
・間違った効果測定では、実態を正しく把握できない
多くの研修では、終了後に満足度アンケートを取ることがありますが、満足度が高い=研修効果が高いとは限りません。また、管理職の成長を評価するためにサーベイを活用するケースもありますが、受講者の心理状態や組織文化によって結果が大きく変わるため、研修の効果測定としては不十分です。
よくある失敗パターン
研修後のアンケートで「講師の説明が分かりやすかった」「プログラムの満足度が高かった」などの評価を得ても、現場での行動変容が伴わなければ、研修の成果とは言えません。
また、組織のサーベイを使って研修の効果を測定したものの、危機感を持った管理職が低い評価をつけたことで「研修のせいで満足度が下がった」と誤解してしまうケースもあります。
対策:適切な方法で効果測定を行い、研修の成果を確認する
研修の効果を正しく測定するためには、研修前後で受講者の変化を確認する仕組みを設けることが重要です。
具体的には、研修後の一定期間後に管理職がどのような行動変容を起こしたかを振り返る場を設け、実際の業務でどのような影響があったのかを確認します。
また、管理職の上司や部下からフィードバックをもらい、研修がどのように現場で活かされているかを把握することも有効です。
サーベイやアンケートを活用する際には、単なる評価ではなく、「どのような学びがあったか」「実践できていること・できていないこと」などを具体的に記載できる形式にすることで、より実態に即した効果測定ができます。
研修の効果測定については「研修の効果測定で迷わない!具体手法4つを公開」でも詳細を記載しています。
2-9. 講師が一方的にあるべき論を提示し、説得している
管理職研修の講師が「あるべき論」を一方的に伝えるだけでは、受講者が納得せず、実践につながらない研修になってしまいます。
その理由は、大きく2つあります。
・受講者が受け身になり、研修内容が浸透しない
講師が理想的な管理職像を一方的に伝えるだけでは、受講者が「現場の実態と合わない」と感じ、学びを活かす意欲が湧かなくなることがあります。
・受講者の状況に合わないと、納得感が得られない
「部下育成は丁寧に行うべき」と言われても、受講者が「現実的に時間がない」「そもそも部下がすぐ辞めてしまう」と感じている場合、講師の話に対して疑問を持つことが多くなります。
その結果、研修で得た知識を実践する気になれず、研修の効果が薄れてしまいます。
よくある失敗パターン
講師が「管理職とはこうあるべき」という話を一方的に展開し、現場の課題に寄り添わないまま研修が進んでしまうケースがあります。
このような場合、受講者は「現実には適用できない」と感じ、研修の内容を自分ごととして捉えられなくなります。
対策:対話を重視し、受講者の実情に寄り添った研修にする
講師が一方的に話すのではなく、受講者との対話を取り入れることで、実際の業務に活かしやすい研修にすることが重要です。
受講者が持っている悩みや課題を共有し、それに対して具体的な解決策を考える場を設けることで、実践的な学びにつながります。
また、研修の企画段階で、「管理職が今どのような課題を抱えているのか」「研修で何を得たいのか」を整理し、受講者に合った内容を講師とともに設計することも大切です。
2-10. 受講者の実情にそぐわない
管理職研修の内容が受講者の状況に合っていないと、研修が意味のないものになってしまいます。
その理由は、大きく2つあります。
・研修のテーマが現状の課題と合っていない
例えば、管理職が「目標達成」に追われているにもかかわらず、「心理的安全性」に関する研修を実施しても、受講者は「今、この学びが必要なのか?」と疑問を感じてしまいます。
・受講者が研修内容を実践できる環境にない
研修で学んだことを実践するための環境が整っていなければ、学びを活かすことが難しくなります。
よくある失敗パターン
管理職が忙しい中で、長時間の座学研修を受けたり、自身のレベルに合わない内容を学んだりしても、効果は期待できません。また、研修内容が業務に直結していなければ、現場で活かすことが難しくなります。
こうした研修では、実践につながらず、ポジティブな成果を生み出せない可能性が高くなってしまいます。
対策:受講者の状況を把握し、最適な研修を設計する
研修前に受講者の課題をヒアリングし、「今、最も必要な学びは何か?」を明確にしましょう。
また、研修の中で「現場でどのように活かせるか」を考える時間を設け、学びの実践につなげる工夫を取り入れます。
例えば、管理職が目標設定に追われているけど心理的安全性を学んでほしい場合は、目標設定・管理を学びながらも、心理的安全性につながっていくチーム力を創っていくにはどうしたらいいかを考えられる設計にするといいでしょう。
2-11. 単発の研修で終わり、フォローアップが不足している
管理職研修を一度きりで終わらせてしまうと、学びが定着せず、現場での行動変容につながらないことがあります。
その理由は、大きく2つあります。
・研修直後は意識が高まるが、時間とともに忘れられる
研修を受けた直後は「学びを活かそう」という意識が高まりますが、日常業務に戻ると、学んだ内容が徐々に薄れ、元の行動に戻ってしまうことが多くあります。
・実践の中での課題を解決する機会がない
研修で学んだことを実際に職場で試してみると、「思ったようにいかない」「現場の状況に合わない」といった壁に直面することがあります。しかし、フォローアップがなければ、その課題を解決できずに終わってしまうため、研修の効果が発揮されにくくなります。
よくある失敗パターン
例えば、1on1スキル向上を目的とした研修を実施した場合、研修直後は「やってみよう」と思っても、実際に部下との1on1を進めるうちに「時間がない」「効果が出ない」といった理由で続かなくなることがあります。
フォローアップがなければ、「研修で学んだことは使えない」と判断され、学びが無駄になってしまいます。
対策:フォローアップを実施し、継続的な学びを促す
研修の効果を高めるためには、研修後のフォローアップをしっかりと設計し、学びの定着を促すことが重要です。
具体的には、次のような取り組みが有効です。
・研修後にアクションプランを作成し、実践の機会を設ける
・1ヶ月後・3ヶ月後にフォローアップセッションを実施し、進捗や課題を振り返る
・受講者同士が学びを共有する場を設け、お互いの成功事例や課題を共有する
これにより、研修で学んだ内容を現場で活かす機会が増え、実際の行動変容につながりやすくなります。
2-12. 適正な予算が配分されていない
管理職研修に適切な予算が確保されていないと、研修の質が低下し、意味のないものになってしまうことがあります。
その理由は、大きく2つあります。
・予算が少なすぎると、効果的な研修が実施できない
コスト削減を優先し、価格の安い研修を選ぶと、研修内容が薄かったり、講師の質が低かったりして、実際に役立つ学びが得られない可能性があります。
・予算を多くかけても、自社に合わなければ意味がない
一方で、高額な研修を実施すれば効果が出るとは限りません。他社で成功した研修を導入しても、自社の文化や課題に合っていなければ、期待した成果が得られないことがあります。
よくある失敗パターン
低価格の研修を選んだ結果、講師の質が低く、表面的な知識しか得られなかったというケースがあります。
また、経営者仲間の紹介で高額な研修を導入したものの、自社の管理職には合わず、学びを活かせなかったという例もあります。
対策:予算内で最適な研修を選び、投資対効果を高める
管理職研修を効果的に実施するためには、予算をどのように配分するかを適切に判断することが重要です。まず、自社の課題を明確にし、その課題を解決できる研修に適正な予算をかけることが大切です。
下記の3点を意識しましょう。
・研修の目的やゴールを明確にし、それに合った研修を選ぶ
・低価格で質の低い研修を選ばず、費用対効果を考慮する
・予算が限られている場合、研修後のフォローアップを重視する
また、研修にかける予算を「単発の費用」ではなく、組織の成長への投資として捉えることが重要です。研修が組織にどのような変化をもたらすのかを考えながら、適正な予算を設定しましょう。
ーーーーー
管理職研修が「意味がない」「効果を感じられない」ものになってしまう原因として、12の失敗パターンを紹介しました。
こうした研修では、管理職の認知や行動の変化につながらず、現場での実践が難しくなります。
そうならないためにも、適切なプロセスで管理職研修を検討しましょう。
3)意味がない管理職研修にしないための5つのプロセス
管理職研修の成功には、「企画」「実施」「フォローアップ」の流れをしっかり設計することが欠かせません。
ここでは、研修を成功させるための具体的な進め方を5つのステップに分けて説明します。
① 研修の目的とゴールを明確にする
意味のある研修にするためには、まず目的を明確にすることが必要です。
研修の目的が不明確なままでは、受講者にとって意義を感じにくく、学びが実践につながりません。
まずは、「この研修を通じて管理職にどんな変化をもたらしたいのか」を整理することが重要です。
管理職研修の目的は、主に次の2つに分かれます。
① 「管理職として求める姿」に近づけるための研修
例)
・新任管理職が役割を理解し、適切な行動を取れるようになる
・組織の方針に沿ったマネジメントを実践できるようになる
② 「自組織の課題解決」を目的とした研修
例)
・部下育成やチームパフォーマンス向上など、現場の課題を解決する
・企業成長のために、次世代リーダーを育成する
まずはどちらの目的で実施するのかを確認し、その後、「研修後に管理職がどうなっているべきか」を具体化します。
例えば、「部下との1on1の頻度を増やし、対話を深める」という行動変容を期待するのか、 「チームのパフォーマンスを向上させるための戦略的な意思決定ができるようになる」ことを目的とするのかによって、研修の設計が変わります。
アーティエンスでご支援する際も、企業ごとの課題を深くヒアリングし、研修の目的を明確にするところから参加しています。
目的とゴールを具体的に設定することで、研修内容の選定や研修後の効果測定が適切に行えるようになります。
② 研修内容を決める
研修の目的とゴールが決まったら、それに沿った研修内容を決めていきます。
ここで重要なのは、単なる知識のインプットで終わらせず、実践につながる学びを内容かを確認することです。
研修内容を決める際に迷った場合は、下記の表を参考にしてみましょう。目的に合った研修内容を選びやすくなります。
| 目的(効果) | 管理職研修の 種類 |
研修内容例 |
|---|---|---|
| ① 管理職の 意識醸成 |
新任管理職研修 | ・マインド醸成 ・役割の理解 |
| ② 次の経営者の 育成 |
次世代リーダー育成研修 | ・戦略思考、事業開発、マーケティング ・財務、会計 ・問題解決(クリティカルシンキング、システムシンキング) |
| ③ チームパフォーマンス・エンゲージメントの向上 | 管理職のパフォーマンス向上研修 | ・部下育成(OJT、1on1、コーチングなど) ・目標管理・評価面談 ・チームとしての業務遂行 ・管理職同士のチームビルディング ・リーダーシップ |
| ④ 労務管理・コンプライアンスのリスクマネジメント | 労務管理・コンプライアンス研修 | ・人事労務管理 ・メンタルヘルス ・コンプライアンス |
③ 研修を実施する
研修の効果を最大化するためには、受講者が主体的に参加できる環境を整えることが重要です。
講師が一方的に話すだけではなく、実際の業務に即した課題を取り上げ、ディスカッションや実践的な演習を取り入れることで、学びを深められます。
なお、経営者の考えを伝える場面では、一方通行にならないよう注意が必要です。
経営者が直接メッセージを伝えることは有効ですが、それを押し付ける形ではなく、管理職が自らの業務と結びつけて考えられるように対話の機会を設けることが重要です。
そのための具体策として、アーティエンスでは経営者が一方的に話すのではなく、対話の場を設けたり、管理職が「自分の業務とどう結びつくのか?」を考える時間をつくるようにしています。
受講者のリアクションを確認しながら柔軟に進め、その場で感じた疑問や課題を共有し合い、現場で活かせる学びにしていくことが、研修を意味のあるものにするポイントとなります。
④ フォローアップする
研修は「受けたら終わり」ではなく、その後の実践が何よりも重要です。
研修で学んだことを現場で活かせるようにするために、フォローアップの仕組みを整える必要があります。
例えば、次のようなフォローアップが効果的です。
・研修後にアクションプランを作成し、一定期間後に振り返る
・研修後1ヶ月以内に、学びを実践する機会を持つ
・3ヶ月後に進捗を確認し、成果や課題を共有する
・バトンメール®を実施する
バトンメール®とは、アーティエンスが開発した、メールやグループチャットを用いた研修の学びのリマインドと相互の成長を促進するためのツールです。
受講生4~5名のグループになり、1週間に1回、「研修で学んだことを現場でどのように活かしたのか、どんな気づきを得たのか」を書いて回していくというものです。これを行うと研修の学びが継続されていくことが期待できます。
本ツールの使い方や注意点は下記から資料をご確認ください。
こうしたフォローアップを行うことで、研修での学びが管理職の行動に根付くようになります。
⑤ 効果測定と改善を行う
研修の効果を確認するためには、単なる満足度アンケートではなく、実際の行動変容を測る仕組みが必要です。
例えば、以下のような視点で効果を測定すると、研修の成果が明確になります。
・行動変容の確認:「研修後に、学んだことを実践しているか?」
・職場での影響:「チームの雰囲気や業務の進め方に変化があったか?」
・上司や部下からの評価:「管理職のリーダーシップに変化が見られるか?」
「① 研修の目的とゴールを明確にする」で設定した目的の方向に向かって進めているのかの中間確認地点となる状況を設定しておくと、確認しやすいです。
効果測定を行うことで、研修の改善点も見えてきます。もし期待した変化が見られない場合は、フォローアップの方法を見直したり、次回の研修内容を調整することで、より効果的なプログラムを作ることができます。
アーティエンスでは、研修後のフィードバックや今後のアドバイスなどを提供しているため、効果の不安や思いがけない変化などもご相談いただけます。
この流れを丁寧に進めることで、管理職が現場で実践できる研修となり、組織の成果につながります。
【あわせて読みたい】
【管理職研修】事例を通して効果的な内容と失敗しないポイントを徹底解説!
管理職研修を4種類に分けて解説!種類ごとの内容を知り、最適な研修を見つけよう
4)まとめ・効果的な管理職研修はアーティエンスにおまかせ
本コラムでは、意味のない無駄な管理職研修になりやすい特徴から、具体的な対策と、研修企画から実施までの進め方についてお伝えしました。
管理職研修の目的は管理職が「認知」と「行動」の両面で変化し、組織の成果につなげること です。
忙しい管理職の貴重な時間と、企業の大切な予算を投じるからこそ、研修が無駄にならないよう、確実に変化を生み出す研修を意識しましょう。
なお、アーティエンスでは、企業ごとの課題に応じた管理職研修を設計・実施し、研修後のフォローまで一貫して支援しています。
「管理職研修を企画したいが、どこから手をつければいいかわからない」
「今の管理職研修が本当に効果的なのか、見直したい」
そうお考えの企業様は、ぜひアーティエンスにご相談ください。
効果的な管理職研修を行い、管理職から組織を変えていきましょう!
意味のある管理職研修を企画したい人事責任者様・担当者様へ
こんな悩みをおもちではありませんか?
- 効果のある管理職研修企画の具体的なプロセスが知りたい
- 予算内でできる最適な研修を知りたい
- 自組織の課題を解決できる管理職研修を知りたい
- 成功事例や研修効果を高めるノウハウを知りたい
当社では、経験豊富な担当者が貴社の課題感や予算にあわせ、効果的な管理職研修を企画いたします。まずはお気軽にご相談ください。